「県別の最低賃金」はどう見ても矛盾だらけだ 「全国一律の最低賃金」は十分検討に値する
つまり、都道府県別の最低賃金は、どのくらいの規模の企業がどれくらいの影響を受けるかを、きちんと分析せずに設定している可能性が非常に高いと断言せざるをえないのです。
私がこのように確信するのに至ったのは、すでに紹介した矛盾の多さに加え、そもそも中央省庁にも十分な分析が可能な統計が存在しないということと、今ある統計を最大限生かして科学的な最低賃金の水準を提案できる分析に長けた人材がいないという、残念な事実があるからです。
例えば、データをしっかりと見れば、最低賃金を毎年5%引き上げた場合、影響を最も大きく受ける企業でも耐えられるという根拠が導き出されます。それなのに地方の中小企業が倒産したり、廃業しに追い込まれると主張するのは、根拠がありません。
もちろん、悪影響が懸念される県もあります。とくに、宮崎、沖縄、青森、秋田の4県は注意が必要かもしれません。別途支援策が必要となるしょう。
ただし、この4県の小規模事業者の生産性が低い最大の要因は、これらの県の企業の規模がとくに小さく、全国の最低水準だからです。彼らにしても、合併によって規模を拡大させれば、最低賃金の引き上げに備えることが可能でしょう。
このように、最低賃金を毎年5%引き上げたら地方は非常に困り、経済が「ヤバいことになる」という意見の根拠が乏しいことは、アナリストなら当たり前に行う分析をすれば、すぐに明らかにできます。
生産性向上には「アメとムチ」が必要不可欠だ
企業の目先の利益だけに目を向け、現状維持に固執し、さらに社会保障の維持の観点を無視するという立場の人間ならば、最低賃金を全国一律にしたり、毎年引き上げることに反対するのももっともです。
しかし、日本経済の最大の柱である個人消費は、人口減少によって減ってしまうので、企業の付加価値を高め、賃金を上げて、備える必要があることは子どもでもわかります。
企業の経営者は、1990年代に入ってから、生産性が向上しているにもかかわらず、非正規雇用を増やしたりして賃金を減らし続け、個人消費に悪影響を及ぼしてきました。付加価値が増えても賃金を上げる気のない経営者には、強制的に賃金を上げさせ、プレッシャーを与える必要があります。
同時に、これからの日本には合併促進政策、輸出促進政策、最先端技術の普及促進政策、それを活用するための社員教育促進策、そして経営者のレベルを上げるための教育政策が不可欠です。
誤解のないように断っておきますが、最低賃金の引き上げは目的ではありません。『日本人の勝算』でも説明したように、日本復活のための総括的な政策を促進するための刺激策、つまりは手段です。
まず生産性を上げてから、賃金を上げるのが正しい順序だという意見の人が多いようですが、ほとんどの経営者は生産性を上げようと努力はせず、現状維持に躍起になっているのが分析結果からも見えてきます。そんな彼らが自ら賃上げの必要性に目覚めるのを期待しても、効果が出るとは到底思えません。
人口減少が本格化し、大変な事態が待っていることを考えたら、何としても腰の重い経営者を動かすためのアメとムチが必要です。だからこそ、生産性向上促進策と最低賃金の引き上げなのです。
次回は、全国一律最低賃金制度を導入したイギリスとドイツで何が起きたのか、エビデンスを検証してみたいと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




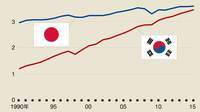


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら