藤は、看取りが多死社会に、経済面でも恩恵をもたらす可能性を指摘する。一例が、生命保険の「リビング・ニーズ特約」の有効活用だ。
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命半年と告知された場合、その被保険者が、保険金の一部を前払いで受け取れる制度。医療費の補助や、余命期間を充実したものにする資金として利用できる。
だが、藤が調べたところ、最高限度額が1人3000万円とされるこの特約は、ほとんど利用されていないという。後者の、余命期間を充実したものにする資金としての活用を、藤は推奨する。
「多死社会を前向きなものとしてとらえ直すために、政府が看取りの重要性について啓発することです。その上で、リビング・ニーズ特約を有効活用すれば、看取りに関わる仕事は、人生の大切な締めくくりと向き合う価値を持ち、やりがいと経済的安定を両立できるものになるはずです」
この連載でも書いてきたように、看取り士にとっての「看取り」とは、人が旅立つ瞬間だけを意味しない。余命告知を受けた本人が心身共に、戸惑いながらも死を受け入れていく過程と、その家族が同様に死を受け入れていく過程の両方を意味する。
看取り士は、本人とその家族の意向を踏まえながら、両方の過程のバランスをとり、誰もが納得できる、温かい最期へ導いていく。簡単な仕事ではない分、やりがいは十分ある。
その業務内容にふさわしい収入が、リビング・ニーズ特約の活用で確保されれば、一つの職業として自立できると藤は見ている。対象は20~30代から団塊ジュニア、さらには団塊の世代にまで広がる。
非正規社員も多い世代に正規雇用が増えれば、結婚する人が増えるかもしれない。年間150万人が亡くなる多死社会が近づく中、「死にがい」と「生きがい」をつなぐ斬新なアイデアだ。
日本が世界の模範になる日

記事冒頭に話を戻す。映画『みとりし』の試写会後にマイクを握った、日本看取り士会の柴田会長は、病院でも施設でも死ねない看取り難民が、2030年に47万人も発生するという推計に触れて、訴えた。
「老いた親が自宅で子や孫に抱きしめられて、次世代に『いのちのバトン』を引き継いで旅立てる国になれば、日本は世界の模範になれます」
柴田が2017年7月にカナダで行なった講演会でも、「死の恐怖とどう向き合えばいいのか」とか、「死にゆく患者にどのように接すればいいのか」という質問が多かったという。現地の医療関係者や一般市民から寄せられたものだ。大多数の日本人と大差ない。
キリスト教文化が根づいている欧米にも、抱きしめて看取る文化が広がる可能性があると、柴田は考えている。看取り士会はすでにカナダにも設立されていて、中国・米国にも看取り士資格を取得した人たちがいる。
連載3回目で紹介した男子高校生が、祖父の死に際して「人生の卒業式なら『おめでとう』だし……」と語った健康的な感受性が、私たちの社会の当たり前になる日は、きっとそう遠くない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

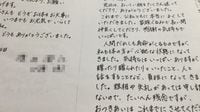































無料会員登録はこちら
ログインはこちら