「あの経験を経て迎えた、父の最期でした。実家に着いて、柴田さんの本に書かれた作法を真似て父親を抱きしめたら、背中はまだ温かかったです。私の子供たちにも抱いてもらいました。いい親孝行ができたと思います」

藤は満足そうに語った。母親が隣でふと昼寝をした隙に、父親は静かに逝ったらしい。
「少しも取り乱すことなく、従容として逝った父の最期を知り、『すごいな』と思うと同時に、自分も子供たちにこんなふうに看取ってもらえるなら、死は全然怖くないと思いました」
口元を少しほころばせながら、藤は言った。以降、藤には父親が自分のそばにいるという感覚が生まれ、その存在感は生前よりも増したという。
父親の看取りとほぼ同時並行で、藤が執筆していた著書がある。表題は「日本発 母性資本主義のすすめ 多死社会での『望ましい死に方』」(ミネルヴァ書房)だ。
あえて極端にかみ砕くと、「高齢化が進んで、たくさんの人が亡くなる時代が来るんだから、今までの暗くて無価値な『死』のイメージを、この際ガラッと変えないと日本ってやばくないか?」という問題提議だ。
「死にがい」と「生きがい」をつなぐ発想転換
2025年の日本は、年間150万人もの人が死ぬ多死社会になるといわれる。まだ誰も経験したことがない事態だ。
「それにもかかわらず、『死は無価値だ』という考え方が今後も続けば、日本社会は回っていかなくなると思います。『望ましい死』でも、『温かい死』でもいいんですが、もっと前向きな『死』の再定義が必要です」
藤はそう強調する。彼は著書でも、前出の柴田の言葉をこう引用している。
「中高年で元気な人たちが死の問題から逃げているが、看取りの体験は特に自己否定の感情が強い男性に大きな変化をもたらし、人生の優先順位が変わるはずである」
藤の視点は、温もりが残る父親の背中を子供たちと抱きしめて看取ることができた達成感、自分もこうして温かく看取られるなら、死は怖くないと思えてつかんだ死生観、さらには従容として逝った父親への敬意と、生きがいならぬ「死にがい」の手応えなどに裏打ちされている。

最後の「死にがい」は聞きなれない言葉だが、この連載2回目で触れた、「人生の最後を病院任せにせず、人としての尊厳を保ち、自分で決めて旅立っていくべきだ」という、元新聞社の論説委員の心構えと重なる。彼は生前、自分の葬儀で流す音楽の選曲と順番にまで心を配った。
あるいは連載6回目で、自然食品販売店主の妻が、介護の末に義母の死に直面して、自分も明日死ぬかもしれないから、「今日一日をしっかりと生きなければいけない」と改めて痛感した、生きがいともつながる。
40年以上も「病院で死ぬ」社会が続いたことで、「無価値」のレッテルが貼られたままの「死」は、むしろ愛情と勇気をもって向き合えば、「生きがい」にも反転するエネルギーを人に与えてくれる。「死にがい」と「生きがい」はコインの表裏だ。
藤も著書で、柴田が会長を務める「日本看取り士会」の理念を、「すべての人が愛されていると感じて旅立てる社会づくり」だと紹介している。

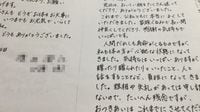































無料会員登録はこちら
ログインはこちら