「トヨタのできる人」が365日実践する3大習慣 生産性の高い職場ほど「ラクをする」
「私は当時、塗装の部門に所属していました。下や横に位置する面を塗装するのはむずかしくはなかったのですが、天井に貼りついている面を塗装するのは簡単ではありませんでした。塗料は液体なので、天井に吹きつけるとどうしても重力で垂れ落ちてしまうからです。この問題に直面したとき、多くの作業者は、『これはできない』と諦めモードでしたが、その上司は、『さあ、どうしてやろうかな』と言って、試行錯誤を始めました。そして、塗料が垂れ落ちないように斜め方向から少しずつ吹きつけるという方法で、この問題を解決しました。
今振り返ってみると、困難な問題に果敢に立ち向かう人ほど、技術も向上していきましたし、昇進もしていきました。むずかしいことにチャレンジすることで、その経験がその後の仕事にも生かされたのだと思います」
トラブルをどう解決するかで今後の仕事にも影響が
なかには、一生に一度しか経験しないような大きなトラブルに見舞われることもあります。そのような重大問題を前にして、及び腰で対処するのか、それとも前向きに解決に向けて動くのか。どちらを選択するかは、その後の仕事にも大きな影響を及ぼします。
まったく同じような問題は起きなくても、そのときに問題解決に奔走したことによって得られた経験は、別の機会で必ず生きてきます。トレーナーの中上は、こう続けます。
「私はロボットに塗装の作業を教える(ティーチングという)仕事もしていましたが、困難な仕事に果敢に立ち向かい、絶えず技能を磨いてきた人は、ロボットにティーチングするのも得意です。カンコツ(仕事をうまくやるための勘やコツ)を理解しているすぐれた技能をもつ人が教えると、ロボットはスムーズな動きで、ムダがない。一方、そうではない人が教えると、ムダな動きが多く、仕事の仕上がりにもムラがあります。誰がロボットにティーチングしたか、すぐにわかるくらい差が出るものです」
誰でもできる簡単な仕事ばかりしていたら、スキルは磨かれません。それこそロボットに代替されてしまいます。一方で、多くの人が逃げ出したくなるような困難に立ち向かうことが習慣化している人は、独自のカンコツを身に付けていきます。だから、工場の自動化、ロボット化が進んでも、その技術を生かすことができるのです。
チャレンジして失敗するかもしれない。しかも、すぐには生産性向上には結びつかないかもしれない。しかし、チャレンジした経験は必ずどこかで生き、付加価値の高い仕事を生みます。「さあ、どうしてやろうかな」。問題に直面するたびに、こんな言葉をつぶやくことが習慣になれば、日々成長できるだけでなく、結果的に生産性の高い仕事につながるのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

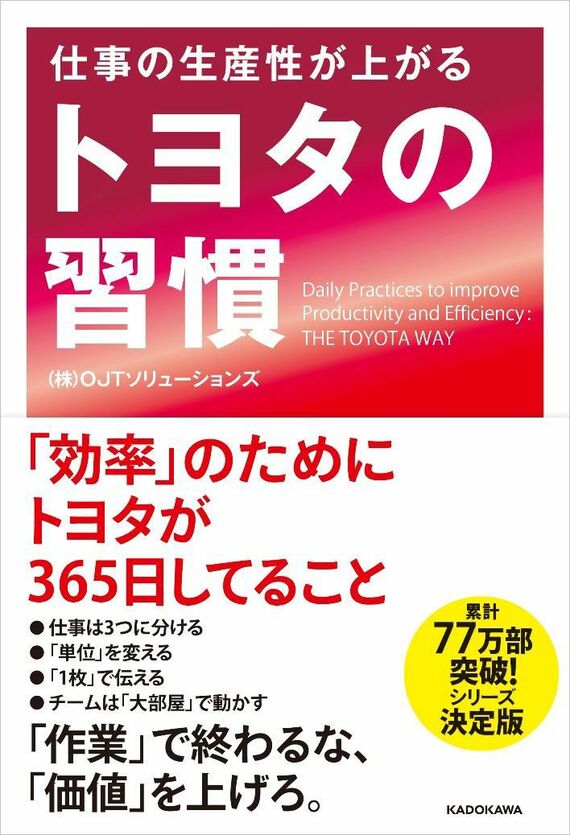






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら