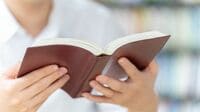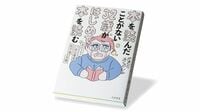「AI選書アプリ」の導入で学校図書館の貸出冊数が2.4倍に増加、"不読層"にも変化をもたらした「ヨンデミー実証実験」の中身
津田小学校校長の滝川昌男氏は、以前から子どもたちの読書の状況について危機感を抱いていた。
「テストの問題文の意図が読み取れているのだろうかと思うような回答が増えていて、子どもたちの読解力の低下を感じています。ゲームや動画視聴に費やす時間が増え、本を読む時間が減っていることが関係しているのではないかと考えています。本校は昔から読書教育を展開してきた学校ですが、学校経営方針にも読書に関する活動を盛り込み、とくにコロナ禍以降、取り組みを強化しています」
そんな中、市教委から声がかかりヨンデミーを導入することになったことについて、図書館主任教諭の鈴木紀予氏は次のように話す。
「親子読書のほか、オリエンテーションや読書週間キャンペーンなどにも力を入れていて、貸出冊数は伸びてはいたのですが、ICTを活用してもっと何かできないかと考えていました。AIの選書アプリを使えるなんて、これはチャンスだと思いました」
本に関する会話が増え、感想提出を楽しむように
津田小学校ではまず、2025年6月から小学1年生の1人1台端末にヨンデミーを入れ、朝の登校後にミニレッスンで本の選び方や楽しみ方などを学び、給食後の10分の読書タイムに読書をして簡単な感想を書くという形で利用を始めた。さらに、タブレット端末を持ち帰り自宅でも使えるようにして、夏休み前までに順次、全学年へと導入を広げていった。

先行した1年生たちは、すぐにヨンデミーに夢中になったという。
「ヨンデミー先生とチャットで会話できるので、『ゲームみたいで楽しい』と言っていました。ほかの子が読んだ本の感想を見て相手にハートマークを送ることもできるので、その交流も楽しいようです。『自分も読んでみよう』と友達が読んだ本を手に取る子もいますし、読んだ本の話で盛り上がったりもしています。1年生はとくに本に関する会話が増えましたね」(鈴木氏)