JR東海リニア「車両の進化」と工事費膨張の明暗 物価高や難工事で4兆円増額、開業はメド立たず
つまり、躯体の形状変更から地上の制御方法、映像投影といったサービス面に至るまで、総力戦で快適性の向上に努めているわけだ。東海道新幹線の最高峰であるN700Sに比べると多少の騒音や振動はあるにせよ、一般的な通勤電車やディーゼル特急に比べれば、快適性は断然高いと感じる。今後もさらなる快適性向上を目指してブラッシュアップされた新しい車両が開発されるのだろう。

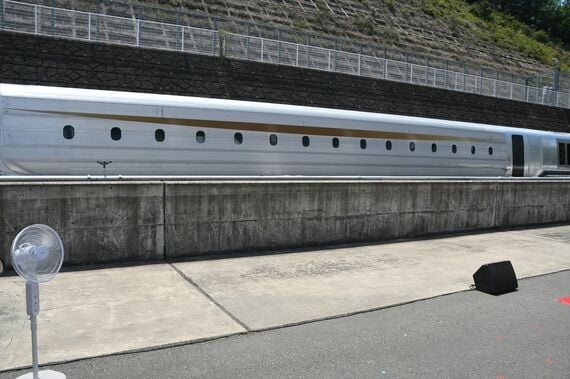
裏腹に、線路などのインフラ建設は順調とは言えない。南アルプストンネルを抱える静岡工区に着工できず、当初27年とされていた開業時期はメドが立たない。静岡工区の工事期間は10年程度が見込まれるため、今すぐ工事に着工しても品川ー名古屋間の開業は35年ということになる。14年の建設工事認可時点で見込まれていた工事費は5.5兆円。その後、21年には7.04兆円に引き上げられた。
工事費はさらに4兆円増
さらに昨今の物価高騰を受け、JR東海があらためて試算した結果、工事費はさらに4兆円増え、11兆円に膨らむことが10月29日に発表された。増加要因で最も大きいのは物価高で2.3兆円の増。現在の物価水準が継続した場合の影響額として1.3兆円、将来のさらなる上昇リスクに備えて1兆円を見積もったという。また、難工事への対応として1.2兆円の増となっている。これまで続けてきた工事の実績を踏まえてのものだという。
巨大な建設プロジェクトの費用は当初見込みよりも増えるのが世の常である。気になるのは、JR東海が費用の増加分をカバーできるのかどうかだ。ピーク時のJR東海の長期債務残高は7兆円を超える。これほどの長期債務を抱える企業はそうそうないが、JR東海は健全経営を維持できると考えている。
理由は、JR東海が東海道新幹線のもたらす収入に支えられた高収益企業であることだ。売上高営業利益率は38%と、JR他社と比較しても頭1つ抜き出る。営業キャッシュフローは6000億円を超え、現在4兆円を超える内部留保は毎年積み上がっている。「さらに社債や借り入れによる資金調達を約2.4兆円行えば、品川―名古屋間の建設に必要な資金を賄え、健全経営と安定配当を堅持できる」というのがJR東海の説明である。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら