国鉄時代の「新幹線運転士」今だから明かす苦労話 雪や台風の走行、0系の「団子鼻の中」に入って便乗
その後、整備掛という雑用をする職に就きました。運転所に宿泊する運転士の起床連絡、寝室のベッドメーキング、事務関係の手伝いなどいろいろなことをやらされました。
試験を受けて合格すると、次は電車掛になります。これは名前の通り、車両の整備をする仕事。検査掛と組んで、検査掛が点検し交換を指示した部品を次々と交換していくわけです。重たいディスクブレーキのライニング板だとか、モーター内のコイルブラシだとかね。黄色いヘルメットをかぶって安全靴を履いて、毎日汗と埃まみれになって働きました。
この仕事を2年9カ月経験した後、ようやく運転士募集試験を受けられる。当時の国鉄は階級制で、最初の整備掛がランク1で運転士はランク7。試験を受けながら上がっていくのですが、けっこう遠い道のりです。
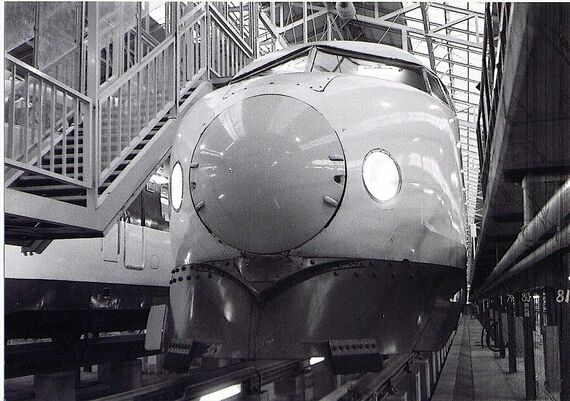
「狭き門」突破し新幹線運転士に
――にわさんは国鉄入社後、どれくらいで運転士になったのですか。
たしか5年くらいでしたから、早かったと思います。新幹線運転士の試験はかなりの狭き門で、合格者はわずか30名。これに対して各新幹線運転所で電車掛に従事する人や在来線の運転士など、数百人が応募していました。
試験は4次試験まであって、1次試験がクレペリン検査。単純な足し算を繰り返し行うものです。2次試験が数学、鉄道法規など5科目の学科試験。
3次試験はパイロットの適性検査のようなものでこれが面白かった。回転椅子に身体を固定し、椅子をグルグル回され、回転が止まったら立ち上がって片足で立つように言われる。それで、どれくらいの時間で正常な感覚が戻るかを試験するわけです。
ほかにも、高速運転の適性を見る検査をいくつかやる。この3次試験までパスするとだいぶ人も減っていて、最後が4次試験の脳波テスト。これらをすべてパスして晴れて運転士候補になるのです。この後、見習い期間を経て本試験合格後、正規の運転士になります。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら