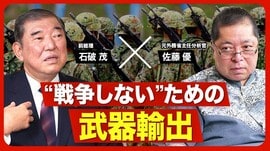マーケットの効率化はもはや善とは限らない--ハワード・デイビス パリ政治学院教授
英中央銀行のアンディ・ホールデイン金融安定化担当理事は、ダウ平均が急落し、30分で1兆ドルの時価総額が失われた10年5月6日の「フラッシュクラッシュ(瞬間的な暴落)」を分析した中で、株式市場の時価総額の増大は金融の発展と経済成長に関連しているかもしれないが、市場の出来高と経済成長にはそうした関連はないと論じている。
米金融市場の出来高は金融危機までの10年間で4倍に増大したが、実体経済は恩恵を受けたのだろうか。ホールデイン理事は注目すべき統計データを引用している。1945年に投資家は、平均で米国株を4年間保有していた。ところが、00年までに保有期間は8カ月に短縮し、08年には2カ月になってしまった。
株式保有期間の急激な短縮と、いわゆる「所有者のいない企業」(そうした企業の株主には、経営陣に規律を課すインセンティブがほとんどない)という現象には関連があるようだ。こうした説明責任の欠如が、金融業界を筆頭に、経営幹部の報酬急増をもたらす一因となった。
出来高の急増により市場は不安定になった
ホールデイン理事の主たる懸念は、市場の安定性についてだ。特に高頻度取引(HFT)がもたらす脅威を案じている。同理事によれば、HFTは、すでに一部の債券や外為市場では出来高全体の半分を占めており、米国の株式市場でも1日の売買の3分の1以上を占める。
HFTがもたらした急速で劇的な変化は今後も続くだろう。取引速度が1秒を切ってから10年しか経っていないが、今ではまさに瞬きほどの速さになっている。HFTに携わる会社は「ゼロに向けた競争」を口にしており、光速級の速さで取引が行われようとしている。