
今年6月に公表された日本経済新聞社と日経HRの「企業の人事に聞いた卒業生が活躍している大学調査」※で、香川大学は「大学卒業生活躍ランキング」で中国四国地方1位、全国でも22位(東大は20位)と高評価を得ました。
入学時偏差値は平均50前後と決して高くはないが、企業採用担当者から採ってよかった大学としての評価が高い。つまり、入ってから伸びるお得な大学と言えるでしょう。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表
小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある
(写真:中曽根氏提供)
その秘密を、大学教育改革の旗振り役として「アクティブラーニング」を推進してきた香川大学 経済学部教授で大学教育基盤センター長(2025年10月1日就任予定)の岡田徹太郎氏に聞きました。
※調査期間:2025年2月28日(金)~4月11日(金)、調査対象:2025年2月現在の全上場企業(新興市場含む、外国会社は除く)と一部有力未上場企業5208社(695社が回答、回答率13.3%)、評価方法:卒業生が職場で活躍している大学を人事担当者に尋ねるもの。各大学の卒業生について、「行動力」「コミュニケーション能力」「知力・思考力」「成長力」の4つの分野で評価


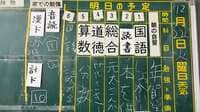





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら