子どもグッタリ「学校の授業が多すぎ」カリキュラム・オーバーロード問題の行方 小学校は5時間、中学校は5.4時間を提案する訳

カリキュラムの「標準時数」に着目
――「カリキュラム・オーバーロード」の実態を明らかにする研究に取り組まれたきっかけを教えてください。

東京学芸大学 現職教員支援センター機構教授
専門は教育学・教育史。1993年東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。東京学芸大学教育学部助手を経て現職。2021年に同大学特別支援教育・教育臨床サポートセンターの教育の現代的課題に関わる研修支援事業(2022年より現代的教育課題に関わる研修支援事業)により開設した防災学習室の運営教員を担当。日本教育学会会員。公教育計画学会会員。教育史学会会員。日本教育史学会会員。近著に『学校の時数をどうするか-現場からのカリキュラム・オーバーロード論』(明石書店)がある
(写真:本人提供)
もう10年ほど前のことになりますが、「子どもたちがなかなか学校から学童に来ないし、来てもぐったりしている」という話を学童保育の指導員から聞きました。そのとき、子どもたちが疲れているのは、学校での教育課程(カリキュラム)に問題があるからではないか、と考えて研究を始めました。
――これまでもカリキュラム・オーバーロードについては、いろいろな研究者が研究してきているのではないですか。
はい。古くは数学者で教育学者の遠山啓さんが「肥大なカリキュラム」という言葉を使って、1960年代の過密すぎる教育課程を批判しています。その遠山さんの指摘に賛同する学校関係者は多くて、1970年代に入ると日本教職員組合(日教組)も委員会を立ち上げて研究しています。
――そうした中で、大森さんの研究の特徴はどこにあるのでしょうか。
カリキュラムの「標準時数」に着目したことです。2020年以降にも「カリキュラム・オーバーロード」という言葉を使った研究がありますが、多くが、増えすぎて子どもたちにも教員にも負担が大きくなった教科の内容についてのものです。遠山さんの「肥大なカリキュラム」というときのカリキュラムも、教科内容のことです。標準時数の歴史的な変遷と、その標準時数がもたらした実態についての研究は、私の知る限り、ほとんどありません。それを今回、私たちがやったことになります。

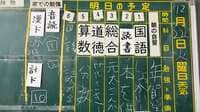































無料会員登録はこちら
ログインはこちら