前述のとおり、ゾウには結核菌が感染することが知られています。
結核は、人では結核菌が主に空気感染によって体内に入り込み、肺に病気を起こす慢性感染症です。かつては不治の病、亡国病、国民病などとも呼ばれ恐れられてきましたが、有効な薬や予防法の普及で激減しました。
しかし、日本は先進国の中でも結核の罹患率は高く、依然として重要な感染症であることには変わりありません。
結核菌にはヒト型結核菌、ウシ型結核菌、アフリカ型結核菌などいくつかの種類があって、種類によってどの動物に感染するかが、ある程度異なります。
人とゾウの間で感染する病気
人に感染するのは主にヒト型結核菌です。また、ウシ型結核菌はウシやシカに感染しますが、人に感染することもあります。
ヒト型結核菌は人以外にも類人猿やそのほかのサル類、イヌ、ウシなどへの感染が知られていますが、ヒト型結核菌のアジアゾウへの感染も、日本を含むアジアや欧米各国でよく知られています。
アジアゾウは結核菌に感染しやすいようで、人からゾウ、そしてゾウから人へも感染することがあります。ゾウからゾウへ感染するのかどうかはまだ分かっていません。
このように動物と人との間で感染する感染症のことを人獣共通感染症と呼んでいます。人獣共通感染症には、動物から人に感染する病気が多いのですが、ヒト型結核菌による結核は人から動物に感染する数少ない人獣共通感染症の1つです。
ゾウは結核に感染していてもはっきりとした症状が出ないことが多く、ゾウの結核予防、早期診断、治療方法の開発はとても重要で、世界中のゾウの研究者が研究しています。
感染して症状が出る頃には病状が進行していることもあるため、発症する前に診断をして治療することが大切です。
また、感染していても無症状の場合、知らないうちにまわりの人や動物に感染を引き起こしてしまう問題もあります。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

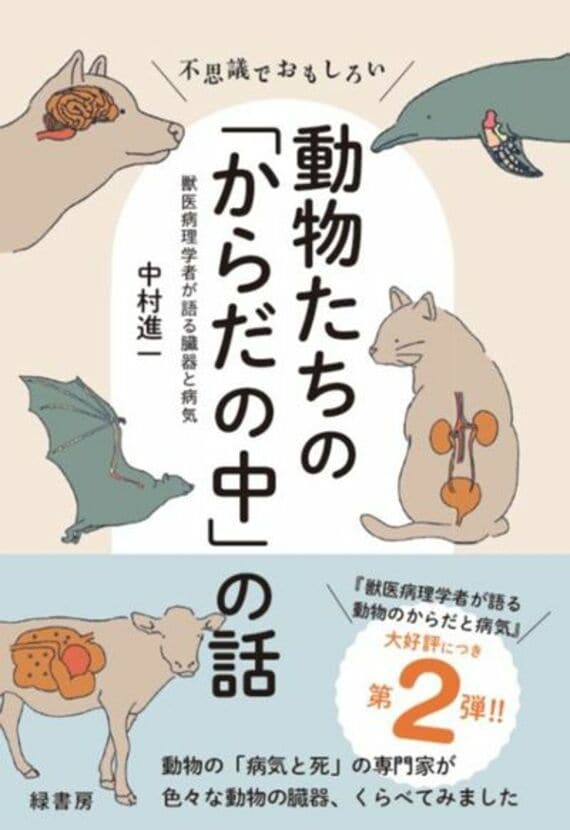






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら