場所が動物園ですので、単に「死因は老衰ではなく、トキソプラズマ症によるものでした」ではすまされません。
この個体がトキソプラズマに感染していたという事実は、最悪、その飼育エリア内のすべてのワオキツネザルがトキソプラズマにさらされていた可能性を意味しています。
動物園内でサル同士が共食いをすることは考えにくいため、おそらく、園外にいた外飼いか野生のネコの糞便に含まれていたオーシストが、ゴキブリやネズミによって飼育エリア内に持ち込まれてきたのでしょう。それにより、餌や水が汚染された可能性があります。
このようなサルの仲間におけるトキソプラズマ感染は、まさに時間との勝負です。
組織切片にトキソプラズマを認めた時点ですぐに獣医師さんに連絡し、飼育ケージの消毒と、同居していたほかのワオキツネザルたちへのトキソプラズマ症に有効な抗原虫薬の投与を行ってもらい、このときは事なきを得ました。
過去にはリスザルが連続死した例も
動物園で飼われている動物が突然死した場合、何らかの感染症や中毒、あるいは飼育環境の急変などの要因が疑われます。
同じ環境下で飼育されている動物は、同じリスクにさらされている可能性が高いため、早急に原因を究明し、有効な対策を打たなければなりません。そうでないと、死が連鎖し、多くの命が失われることになります。
今回のワオキツネザルの事例では、病理解剖を依頼した飼育員さんの適切な判断と、迅速な病理診断、そしてその後の対策が功を奏しましたが、僕は過去に、やはりトキソプラズマによって動物園で飼われていたリスザルが連続死したケースも経験しています。
動物園の飼育員さんや獣医師さんは、動物たちの健康と衛生の管理を日々徹底されていますが、それでも不幸にして死が起こってしまうことはあります。
そんなときは、僕たち獣医病理医が死後の病理診断を通じて「遺体の声」を聞き取り、死因を突き止め、その死が連鎖したり再発したりしないよう、得られた情報を広く共有していきます。
動物園や水族館で暮らす動物たちの健康は、こうした努力の積み重ねによって守られているのです。
この夏、みなさんが動物園や水族館に訪れる機会がありましたら、そこでいきいきと暮らす動物たちの背後にあるこれらの取り組みにも、思いを馳せていただければ幸いです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
















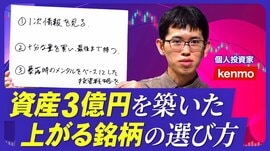




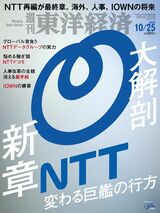









無料会員登録はこちら
ログインはこちら