《疲弊する現代人に》東大卒の名門校教師がおすすめする“哲学のハードルを下げてくれる本”5冊
「私とは何か?」というのは哲学における重要な問いの1つですが、自分がどんな人間なのか分からなくなったり「本当の自分」探しに苦しんだりした経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
作家の平野啓一郎さんは、そうした「本当の自分」「自分らしさ」探しの風潮に抗って、「人間は唯一無二の個人(individual)ではなく、複数の分人(dividual)である」という新たな人間像をこの本の中で提示しています。
哲学入門書というよりはエッセイに近い本ですが、三省堂の国語教科書にも採用された名著です。昨年には『自分とか、ないから。』(しんめいP著/サンクチュアリ出版)という東洋思想の入門書がベストセラーになりましたが、その背景には多くの人が「本当の自分」「自分らしさ」を追い求め、疲弊していることがあると考えられます。
「あなたはどのような人間なのか?」という開示を求められる機会は人生の様々な局面で生じますし、近年はそうした機会に直面する時期が以前より早まっている気がします。「自分らしさ」探しに伴う生きづらさが増している時代だからこそ、「複数の自己を受け入れる」という平野さんの考えがひとつの処方箋になり得るのではないでしょうか。
「なぜ人は働くのか?」というのも哲学における重要な問いの1つですが、「他者と働く」という営みも生きづらさに結びつきやすいものです。
著者の勅使川原真衣さんは、働くことに伴う生きづらさの原因を能力主義に求め、教育社会学と組織開発の視点から能力主義を批判しています。そのうえで、「能力による選抜」によらず関係性の中で組織開発を進めていく方向性をこの本の中で提示しています。
なぜ私たちは、「能力」が足りないのではと煽られ、自責の念に駆られてしまうのでしょうか? 日頃から忙しく働いている中では、なかなかこうした問いを立ち止まって考える余裕がないと思います。




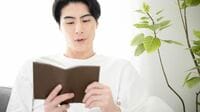




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら