三井銀行が「慶応卒だらけ」だった歴史的な背景 東大出身が屈した「財閥内に学閥」がある世界
中上川の女婿で、のちに三井銀行のトップになる池田成彬は、大阪支店に派遣される際、中上川から実務をするなと念押しされている。
「私は大阪にいけといわれたが、普通の社員としていくことになった。ただ私がいく時に中上川から内命があった。『お前を大阪支店にやるが、向うへいくと支店長はお前に預金係長とか何とか仕事をさせるだろうが、それはやる必要はない。いい加減にしておけ。ただ、だいたい大阪というものについて観察をし、大阪支店のだいたいの動き方を見ておれ。つまらない仕事はしなくていい』こういわれた」(『財界回顧』)。
三井財閥を飛び出す「中上川チルドレン」
西洋文明を直に見てきた中上川は、三井のカネを使って日本の産業を振興させようと考えていた。産業勃興期のメーカーが経営不振に陥ると、部下を送り込んで再建し、三井に取り込んでいった。
代表的な事例でいうと、鐘淵紡績の武藤山治(1867〜1934)、王子製紙の藤原銀次郎(1869〜1960)、大日本製糖の藤山雷太(1863〜1938)、三越呉服店の日比翁助(1860〜1931)などである。
ところが、中上川が死去し、三井財閥が中上川の工業化路線を否定すると、それら企業は三井から放り出され、中上川チルドレンも三井を離れてしまう。かれらは三井財閥と適度に距離を保ちながら、三井のシンパとして経済・財界活動を行った。こうした傍系会社の存在が三井財閥をより大きい存在に見せていた。
中上川彦次郎が死去すると、かねて中上川路線を苦々しく思っていた井上馨、益田孝は三井家同族会理事・早川千吉郎を三井銀行専務理事(同行の事実上のトップ)に転出させることを早々に決めてしまう。井上等は慶応OBが中上川の後任となり、中上川路線を継承することを危惧していたらしい。

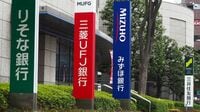






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら