不良債権処理の筋書きを描いたバンカー、「共同債権買取機構」「産業再生機構」の舞台裏をいま明かす。

2003年4月、日本の不良債権処理の遅れに対する国際的な批判が強まる中、産業再生機構が発足した。その1年前、財務省の武藤敏郎事務次官が東京三菱銀行の岸暁会長の元を訪問した。不良債権問題を解決するためのスキーム作りを財務省のチームで検討しているが、実務的な視点がどうしても欠落する。手伝ってもらえないかという相談だった。
岸さんは「うちには知恵者がいるからお任せください」と応え、呼び出された私が会長室に伺うと、「そういうことになったから、手伝ってやってくれ」となった。当時、私は三菱東京フィナンシャル・グループの初代企画担当である経営政策部長。不良債権問題の最終処理に道筋をつける手綱を託された。
当時の銀行は不良債権処理をめぐっていくつかの課題を抱えていた。その1つが、銀行のバランスシートから不良債権が切り離されていないと見なされていたことだ。それまでの共同債権買取機構は銀行出資で運営され、回収後に損金が確定するため、不良債権が金融システムにとどまっていると批判された。
また、「メイン寄せ」によってメインバンクの不良債権がどんどん増えてしまうと、その銀行が耐えられなくなるとの不安が金融界にあった。そこで準メイン以下の債権を産業再生機構に切り離し、メインバンクとの二人三脚で再生に取り組むスキームを描いた。最初は企業再生機構という仮称にしていたが、業界再編の役割を持たせるため産業再生機構という名称にした。
説明のため財務省に行くと、対応してくれたのは畑中龍太郎さんや内藤純一さん、小手川大助さんなど同世代の行政官。財務省が官邸に案を持っていったところ小泉純一郎首相が「よしこれでいこう」となって、総合経済対策に「産業再生機構(仮称)を創設」の文言が盛り込まれた。
金融庁も当時、不良債権処理を進めるため「金融再生プログラム」を策定していたが、産業再生機構の話は寝耳に水。「いったいどこから出てきた話なんだ」と大騒ぎになったらしい。が、産業再生機構と金融再生プログラムの両輪で日本の不良債権処理が大きく前に進むことになる。
東京への帰任命令
私は国際派として海外で活躍したかったのだが、日本が不良債権処理に苦しんだ10年間は、私もこの問題にどっぷりとはまることになる。
1992年8月。当時はニューヨークの三菱銀行米州本部に勤務していたが、東京の本部から「日本に帰ってこい」と言われた。配属先を聞いたら、全国銀行協会連合会の会長に就任していた若井恒雄頭取を支える企画部別室だという。何をするのかを尋ねたら、「日本の不良債権問題を解決するためのスキームを作ってくれ」と言われた。寺東一郎室長と永易克典副室長に何人でやるのか聞いたら、「おまえ1人だ」と言われて面食らった。

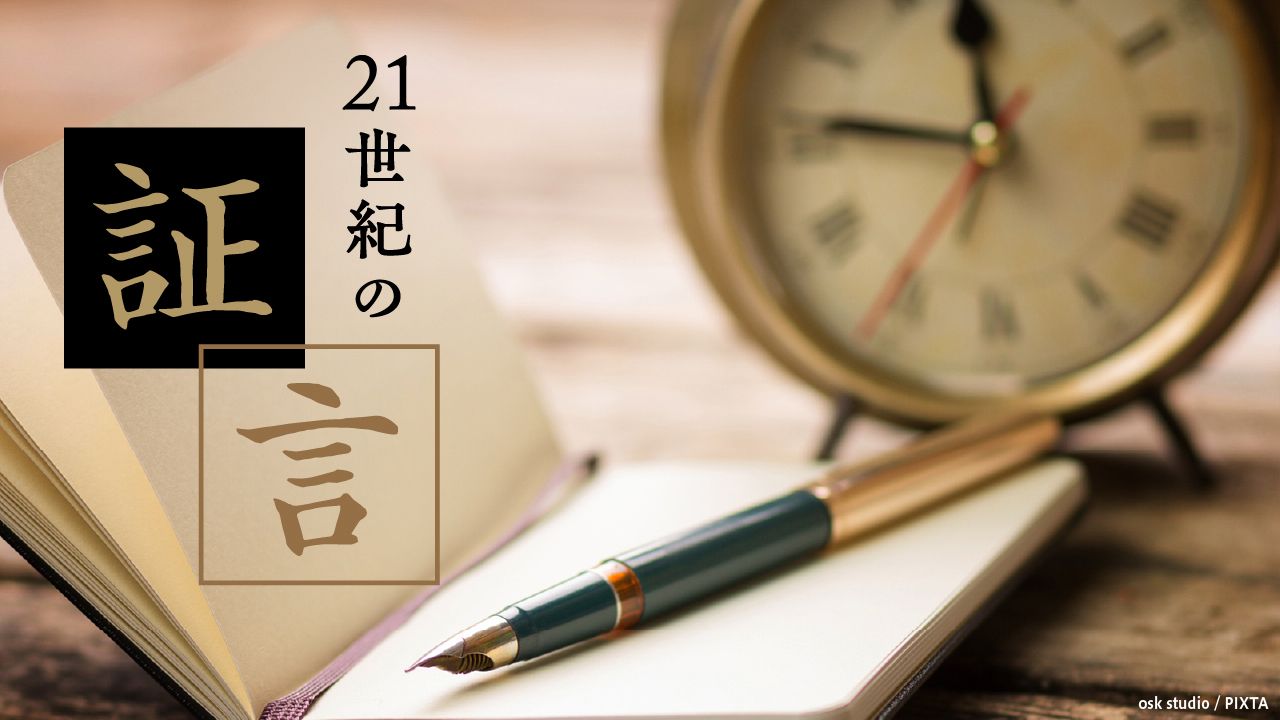































無料会員登録はこちら
ログインはこちら