「リネン係がおらず、部屋を閉鎖…」「観光客は来るのに、従業員がいない…」《働く人の給料が安すぎる》のは、日本の観光業の大問題だ
たとえば、別の記事(日本の観光業を苦しめる「"安すぎる"値付け」問題)でも紹介したように、熊野古道のガイドさんが1人で何人も相手して山道を案内しても、報酬は7時間で1万5000円という話がありますが、一方で昨今の富裕層ツーリズムではエージェントを使って日本に来るようなお金持ちが少なからずいます。
彼ら彼女らは、気に入ったガイドを指名して案内してもらい、滞在中に1000万円落とすこともザラです。ガイドさんに渡るチップも1回の旅行で数十万円、なんて話を聞いたこともあります。
地域の「参入障壁」を見直すことも必要かつ重要だ
今の日本がやりがちなのは、「値付けができずに安く出しすぎてしまっている」ということ。地域の人が提供するアクティビティが「地元民のなんとなくの感覚」で値段がつけられていて、安すぎたりしています。
「飲食店を経営しながら観光コンテンツを売っているようなケースが多いから、適切な値付けがわからない」「ずっとその地域にいて『俯瞰してみた本当の価値』がわからなくなってしまっているから、高く売れない」という状況を招いてしまっているように見えます。
「地域の人しか知らない沢を上る」「少し歩くとサンセットがきれいなビューポイントがある」「透き通るような渓流でカヌーが楽しめる」など、「本当は3万円で売れるかもしれない観光コンテンツ」を3800円で売ってしまっていることもあります。
そのため、そこでしかできない素晴らしい体験やエクスクルーシブな体験は、もとより高い価格で売れるかもしれないのに、先んじて「3800円で売ります」という事業者が台頭してしまうから新規参入もしづらい状況になっているのです。
地方の過疎化や外国人労働者の減少という問題ももちろんあるのですが、こうした地域の「参入障壁」を見直すことも、これからの観光業界に必要で重要なことではないでしょうか。
このような小さな見直しを進めていくことが、観光業界の「給料安すぎ」「稼げない業界」の解決にもつながっていくと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

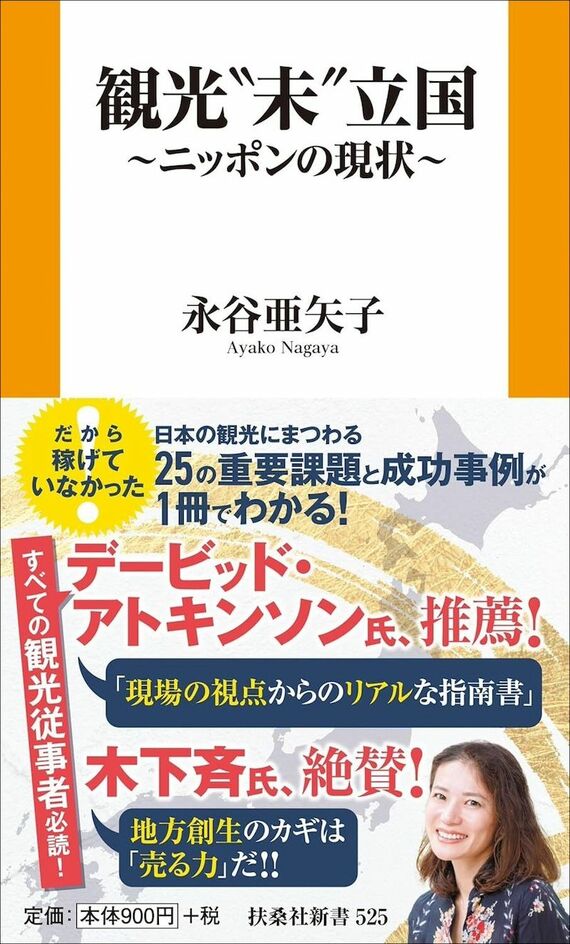






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら