アテンション・エコノミー(関心経済)の暴走の先にあるのは、「アテンション・ハッキング」の氾濫であり、全体としては「公益性のカオス」を招来する可能性が高い。前者は、この危なっかしい生態系を自己の利益のために逆手に取ることを意味し、後者は、社会課題の優先順位が崩壊することを意味する。
今回のフジテレビの会見は、まさにこの生態系のメカニズムにうまく便乗したところがある。

ジャーナリストが目撃した、会見の異様っぷり
ビデオジャーナリストの神保哲生氏は、会場脇に水のペットボトルが何百本も用意され、400個のパイプ椅子に臨時の電源が引かれ、初めから長期戦覚悟だったことや、参加者を限定せずメディア側の罵声や無礼な言動、自称記者の演説などを放置したことを踏まえて、「巧妙なダメージコントロールだった」と結論付けている(大演説に怒声、「ショー化」が生んだフジ記者会見 メディアの責任は/2025年1月31日/朝日新聞デジタル)。
「あの状況で会見を開けば、本来『0―10』でフジの完敗です。ところが、『罵声』に耐え続ける姿を配信することで『2―8』あるいは『3―7』まで持っていけた」と総括し、その真因として、ネット登場のにより「会見そのものが記者の質問も含めて『見られ消費される』場」になったことを指摘した(同前)。
「『見られ消費される』場」とは、アテンション=注意・関心が発生するところであり、そこにおいていかに有利なポジションを築くかが焦点となる。フジテレビは、アテンション・エコノミー(関心経済)の特性を念頭に、あえて玉石混淆の舞台を設け、不愉快なノイズを排除しないことによって、むしろ人々の非難の矛先を一定程度分散させることに成功したといえるだろう。
これは、いわばアテンション・ハッキングと呼べるものであり、今後も大企業からインフルエンサーに至るまで、新たな生態系に適応したダメージコントロールに磨きをかけていくことは想像に難くない。
人々の注意・関心の高まりに乗じて、別の人物や対象にスポットを当てる、混乱を作り出して受け流す、等々の手法の洗練化である。
この問題の厄介なところは、何が事実で何が真実かといったことよりも、相対的に注意・関心が引かれることに好悪の念を抱きがちで、そこから疑惑や信頼性を感じ取りやすいことにある。
結果的に人々の注意・関心を適切に誘導することができた者が得をすることは言うまでもない。
ここにおいてわたしたちはただのユーザーや傍観者ではない。意識の上で、わたしたちは多様なメディアのフィルターを通して「悪者とされる人々」を嬉々として懲罰し、その転落を見守っているのだ。文春砲に対するアンビバレントな感情がそれを如実に表している。自らが透明な権力の一部になったかのような愉悦と恐れである。
誰もがデジタル世界の兵士であることから逃れられない昨今。試されているのはわたしたちの頭脳そのものなのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

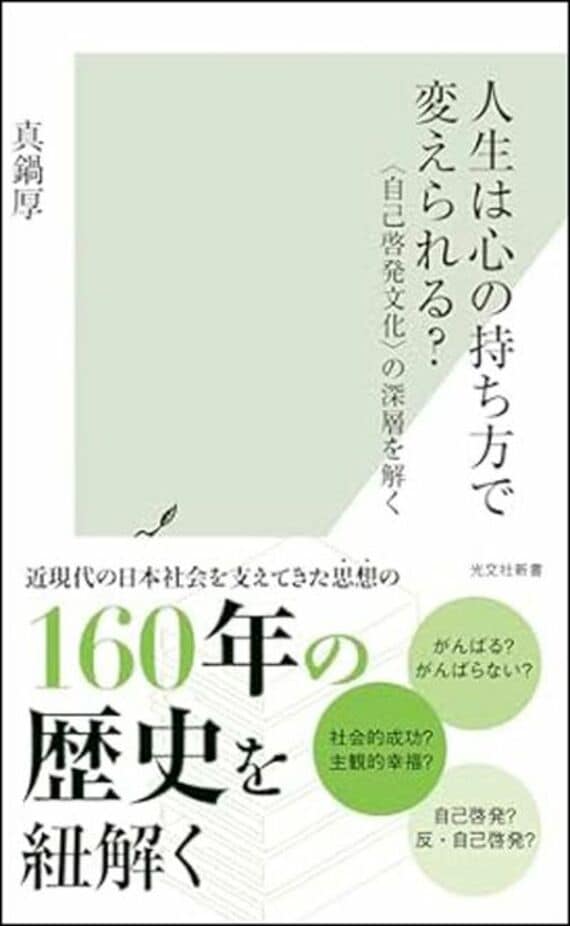






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら