あちこちから葬送に参列する人々や、寺々の念仏僧たちが集まり、広大な野原は埋め尽くされる。桐壺院はもちろん、藤壺、東宮からの使者、そのほか各所からの使者も次々にあらわれ、言い尽くせないほどの哀悼の言葉を述べる。左大臣は立ち上がることもできず、
「こんな老齢の末に、若い盛りの娘に先立たれ、悲しみのあまり足も立たず這(は)いまわることになろうとは」と、我が身の不運を恥じて泣き濡れるのを、大勢の人々が痛ましく見つめることしかできないでいる。
夜通し、大層な騒ぎの盛大な葬儀が行われたが、じつにはかない遺骨のほかは何も残らず、夜明け前のまだ暗いうちに帰ることとなった。人の死は世の常ではあるけれど、人の死に目に会うのは一度か二度しか経験していなかった光君は、たとえようもないほど葵の上を恋い焦がれている。八月二十日過ぎの有明(ありあけ)月の頃なので、空もまた悲しみをたたえているような風情(ふぜい)だ。さらに、子に先立たれた悲しみに沈み、取り乱している左大臣の姿を見て、それも無理からぬことと痛ましく思い、光君は空ばかり眺めている。
のぼりぬる煙(けぶり)はそれとわかねどもなべて雲居(くもゐ)のあはれなるかな
(立ち上っていった火葬の煙は、雲と混じり合って判別がつかないけれど、空のすべてがしみじみとなつかしく思える)
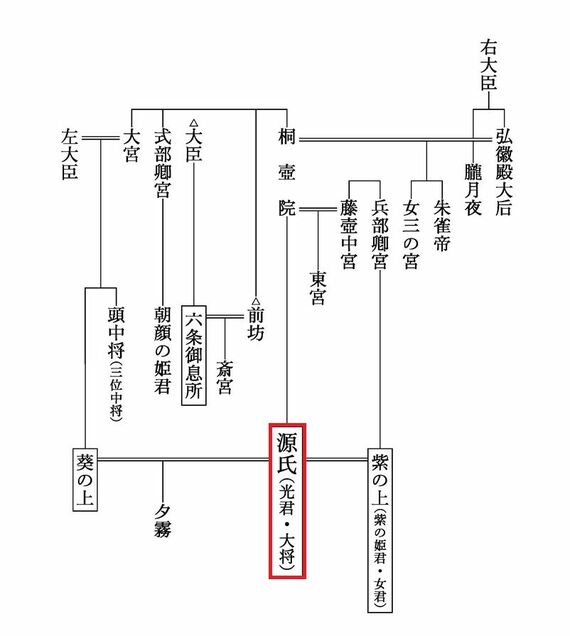
取り返しのつかないことばかり思い出す
左大臣家に帰ってきてからも、光君は一睡もできず、葵の上と夫婦であった長い年月を思い出しては、思う。
どうして、いつかは自分の気持ちをわかってくれるさ、などとのんびりかまえて、気まぐれな浮気なんてして、恨まれるように仕向けたんだろう。夫婦になってからずっと、この私のことを、心を許せない気詰まりな夫と思ったまま、一生を終えてしまったのだな……。
どうにも取り返しのつかないことばかり次々と思い出すけれども、今となってはどうしようもない。鈍色(にびいろ)の喪服を着るのも、夢を見ているようである。もし自分が先に逝っていたら、あの人はもっと濃い鈍色に染めていただろうと思うとまた悲しみがこみ上げる。
限りあれば薄墨衣(うすずみころも)浅けれど涙ぞ袖(そで)をふちとなしける
(妻を亡くした場合のしきたり通り喪服の色は薄いけれど、悲しみは深く、涙は袖を淵(ふち)としてしまう)





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら