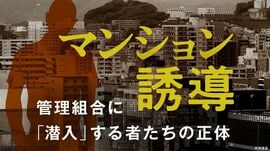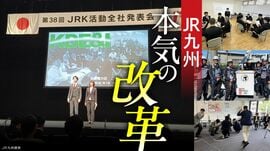文学部地理学科では、2004年度より自己推薦入試を実施しています。この入試制度は、従来実施している一般入試・大学入学共通テスト利用入試とは別の選考方法・基準により入学者を募集するものです。地図を眺めていると時間を忘れてしまう人、三度のメシより地理が大好きだという人、そんな人の応募を歓迎します。選考方法は、第一次選考として書類審査(調査書、志望理由書)を行い、その合格者に 対して第二次選考(筆記試験「地理B」、面接試験)を行います。
なんと、「地図が好き」「地理が好き」という人を募集する、というのが大きく表明されているのです。このように、「1つの分野について突き抜けた個性を持っている人かどうか」が評価されるのが、選抜入試の特徴だと言えるでしょう。学校の成績がいいか悪いかではなく、突き抜けた個性があるかどうかが評価の対象になっているということがわかるでしょう。
実は東京大学も、2016年度入試から学校推薦型選抜入試を行っています。一般入試で合格する人の人数が3000人程度なのに対して、東大の推薦入試の定員はわずか100人。今年で9期になりますが、合格者は1000人にも満たない人数になります。
その試験形態は学部によって細かい部分は異なりますが、基本的にはどの学部でも、志望理由書の提出を求める1次試験と、その後で教授の面接も含むさまざまな形態の試験を課す2次試験とに分かれていて、その後に実施される共通テストの点数の結果を加味して、合格不合格が判断されます。
学部によって、この2次試験の内容が分かれるのが特徴です。例えば教育学部ではポスターセッションと呼ばれる発表が課されます。A0判のポスター1枚の持ち込みが認められ、そのポスターを使って自分の今までの活動に対する発表を行い、そのほかの受験生も参加して質疑応答が行われるというものです。
そしてそれが終わった後では、東大の先生を含む面接官との個別面談が課され、質疑応答が行われるのだそうです。あくまでこれは教育学部の事例であり、例えば法学部ではグループディスカッションが課されるなど、まったく異なる形態の試験が課されます。
どんな子が推薦で東大に合格しているのか
面白いのは、われわれが持っている東大推薦生たちのイメージと、実際の彼ら彼女らとのギャップです。「数学オリンピックで入選した」とか「コンテストで優勝した」とか、そういう実績がある人ばかりが評価されると考える人は多いと思いますが、実際にはそういった実績があるかどうかではないポイントで評価されているそうです。
もちろん、そういう実績を持っている人も受験するのですが、「こんな実績があります」という部分を強調して語っている人は、むしろ不合格になっている割合が多いのだそうです。では、どういうポイントが評価されているのかというと、やはり「個性」です。東大推薦生たちに話を聞くと、その独自性・「突き抜けている度合い」に驚かされます。