石橋湛山は生涯をかけて言論と行動の一致を目指した。

石橋湛山は、自己(自国)の自立と他者(他国)への寛容は両立できると信じる人だった。互いに自立して商売をすれば互恵(win-win)の関係を築けるのだという信頼が、小日本主義にも通底していた。
だが、この論理には「戦争状態でなければ」という前提がつく。戦時期の湛山はこの前提が外れてしまう厳しい現実に直面する。
植民地放棄を唱えた1921年の社説「一切を棄(す)つるの覚悟」を書いた頃の湛山は「排日は国民意識の覚醒を表示するもの」と述べ、中国の排日運動をナショナリズムの覚醒と捉えた。日本も明治維新で近代国家を築くのに苦難を伴った。国土の広い中国で混乱が生じるのは新国家の「生みの苦しみ」であると寛容を呼びかけたのだ。
植民地領有を容認するように
ところが満州事変後の上海事変(32年)が起きた頃から「残念ながら支那人には果して自国を統治する能力あるやが疑われないでもない」と疑念を示し始める。満州国についても「既にここまで乗りかかった船なれば、今更棄て去るわけには行かぬ」と傀儡(かいらい)国家の存在を受け入れるようになった。


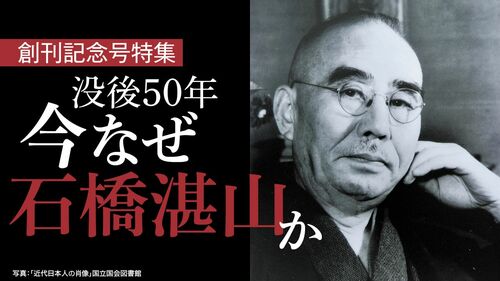


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら