上野:あともう1つ、原因としてありうるのは、彼らは開発パイプラインをずらっと並べているんですね。おそらく1つひとつイチから開発して、1つひとつ治験をしていたのだと思います。開発のコストも治験のコストも莫大になるので、思ったような成果をあげられなかったのではないでしょうか。
私たちはそういった観察から、塩野義製薬さんと販売提携契約を進めました。パイプラインについても、ゼロから1つずつ作るのではなく、モジュールの組み合わせで効率的にアプリが作れるようにした。治験もブロックチェーンによって、極力コストを減らそうとしています。
これらのモデルは世界に通用すると思います。
井上:世界の医療に貢献できるアプリとプラットフォームというのは素晴らしいですね。日本発の医療イノベータとして頑張ってください。
SUSMED 設立:2015年 所在地:東京都中央区 資本金:3066万1000円 市場:東証グロース 従業員数:39名
経営学者・井上達彦の眼
自らをその世界に埋め込むからこそ実現するイノベーションとは何か。
それは、既存のネットワークや資源を生かしつつ、それを別のネットワークや資源と結びつけるというものに他ならない。中心に位置していたがゆえにわかる課題やポイント、そしてそれを解消するために外部の世界に結びつける。社会ネットワーク論では、これを橋渡しとか越境と言われる。
実際、上野さんはこのような起業家行動によって、既存の価値観や制度の大切な部分を尊重しつつ、時代の変化に対応しようとしている。
興味深いのは、越境新結合によってある種の優位性が生まれやすい点である。
上野太郎さんが率いるサスメドは、治療アプリに特化した技術、DTx全般に使える技術、ブロックチェーンと自動解析などの知財を有している。そして、医療の機関へのアクセスや、学会のネットワーク、制度的な障壁についての深い理解、科学技術にかかわる助成金獲得のノウハウなども有している。
これら1つひとつは、それ自体で持続的な競争優位の源泉とはなり得ない。ライバル他社も時間をかければ模倣できるかもしれない。しかし、それらが組み合わさるとシステム優位が実現する。強いものが組み合わさって、さらに強くなるという掛け算の論理である。これが実現するとライバルもなかなか模倣できなくなる。
サスメドの場合、このシステム優位ができた背景には、上野さんの越境ネットワーキング行動があった。しかもその越境可能性は、ITから医療への越境よりも、医療からITへの越境のほうが実現しやすいという非対称性があるように思われる。一つのネットワークに閉じているライバルたちには真似できないし、越境に長けたITの世界の起業家たちであっても、なかなかそれが実現しないのである。
中心に位置する正統な起業家による越境ネットワーキング行動というのは、外部から仕掛ける破壊的イノベーションのアンチテーゼとなるのかもしれない。
スティーブ・ジョブズは「海軍に入るぐらいなら、海賊になれ」と言い放ったが、海軍にしかできないイノベーションもある。日本の産業社会にとっても、良きお手本になるのではないだろうか。




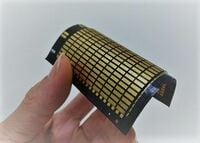





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら