日経平均再浮上の「重要サイン」が点灯しつつある 3万4000円突破に必要な「3つの条件」とは何か
パウエル議長の強気発言の背景には過去数カ月、アメリカ経済の粘り強さを印象付ける指標が相次いでいることがある。求人件数が高水準で推移する中、雇用者数は順調に増加し、消費者の心理も改善傾向にある。アメリカ経済の約7割を占める個人消費が堅調なペースを維持しているのも理解できる。
しかも、ここに来て金利上昇に脆弱であるはずの住宅市場のデータも改善傾向を強めている。建設業者の景況感を示すNAHB住宅市場指数は2023年に入って改善へ転じたが、それを後追いする形で住宅着工件数や新築住宅販売件数が増加傾向をたどっている。
さらに、製造業も持ち直しの兆候がある。8月1日に発表された7月のISM製造業景況指数は46.4へと改善し、6月の46.0から底打ちした。調査項目の内訳からは、新規受注が増加方向に動く反面、在庫が減少方向に動くという望ましい傾向が垣間見えた。このように、底堅さをみせるアメリカ経済は日本株のエンジンとして機能しよう。
半導体関連の動向を把握できる指標が軒並み改善
最後の3つ目、日本株のエンジンとして最も注目すべきは半導体であろう。それは長期的に日本株が半導体の需給に大きな影響を受けてきたからにほかならない。日本株の代表的指数において半導体製造を直接手がける企業の存在感は大きくない。
だが、半導体製造装置や半導体の部材、あるいは半導体の加工に用いる化学品など「広義半導体」で見ればその存在感は大きいため、半導体市況を読むことが極めて重要になってくる。
その広義半導体の動向を把握するために、経済産業省が公表する鉱工業生産統計の「電子部品・デバイス工業」に注目すると、6月の生産は前月比プラス6.8%だった。生産指数の水準は98.3(2020年=100)へと上昇し2019年平均(98.7)に接近。前年比ではマイナス8.6%へとマイナス幅を縮小した(5月はマイナス12.1%)。
2022年以降はノートPCやスマホなどの需要減衰を背景とするシリコンサイクルの悪化に巻き込まれ、日本のIT関連財企業はその勢いを失っているが、ここへ来て底打ち感がみられている点は朗報である。
この持続性を点検するために「製造工業生産予測調査」に目を向けると、向こう2カ月の生産計画は7月にプラス8.0%と大幅増産となった後、8月はマイナス0.9%と微減にとどまる強気な計画であった。















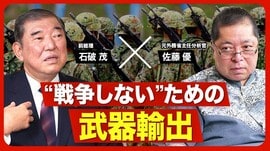















無料会員登録はこちら
ログインはこちら