「ほめる教育」で自己肯定感は高まらない衝撃事実 子供を叱らない大人が増えたのは「エゴ」ゆえか
その一方で、けっして叱らず、ひたすらほめるといった最近の風潮に、不満をもつ子どもも出てきています。
ある小学校で校長をしていた塩澤雄一は、5年生のときに荒れて手がつけられなかったクラスが、6年生になり担任が替わったら全員が落ち着いて授業に集中するようになり、子どもたちはこれまでと違って別人のように素直になったと言います。
そこで、かつて荒れていたやんちゃ坊主たちを集めて、「君たちは5年生のときにあんなに先生の言うことを聞かなかったのに、どうして6年生になったら素直になったのか」と尋ねると、ある子が「前の先生は僕らが悪いことをしても何も言わないから悪いことばかりしていた。今度の先生は、僕らが悪いことをするとちゃんと叱ってくれる。だから先生の言うことを聞くんだ」と答え、ほかの子もそれに頷いていたそうです(『児童心理』 2010年1月号 金子書房)。
また、朝日新聞の「声」という読者の投稿欄に、「なぜ先生は叱ってくれないの?」という14歳の中学生の投稿が掲載されたことがあります(2016年7月31日付朝刊)。私は、その投稿に対するコメントを求められました。9月28日の同欄に私のコメントとともに再掲載された投稿は、つぎのようなものでした。
まるで小学校低学年への対応のようだと私は思った。もちろん騒いでいた生徒が一番悪いのだが、それをしっかり叱らない先生にも問題があるのではないかと思う。
先生だって人間だから、叱りたくないのはわかる。生徒に良い印象をもたれたい気持ちもあるだろう。(中略)
でも、私はそういう先生が嫌いだ。多少やりすぎと言われても、生徒を第一に考え、本気で怒り、叱ってほしい。
私の両親の子ども時代、悪いことをすれば立たされ、竹定規で叩かれたと聞く。でも両親は感謝しているという。いつから先生は本気で叱らなくなったのだろう。(中略)先生、私たちを本気で叱って下さい」
大人がなぜきちんと叱らなくなったのか。そこに潜む利己的な思いを子どもたちはしっかり見抜いているのです。生徒のためではなく、自分かわいさゆえに叱らなくなったのだ、と。
ほめるだけでは自己肯定感は養われない
私が話した内容の要旨として掲載されたコメントは、つぎのようなものでした。
「大人が子どもを叱ることの重要さを訴えています。『ほめて育てる』が人気で、叱るのは不人気な時代。叱るにはエネルギーが要るし、嫌われるかもしれない。良い人と思われたいのが人情。先生なら保護者や管理職の目も気になる。事なかれになりがちです。
『心が折れる』という言葉がありますが、子どもの心は柔軟で、叱られても簡単に折れない。むしろ、叱られた経験がない子は打たれ弱く、傷つきやすくなり、きつい状況で頑張れない。そこに若者の生きづらさがあります。
『遅刻を叱られたからバイトをやめた』という学生さえいますが、これでは社会に出てから困ります。そうした若者が教師や親になり、『叱らない』教育が続く悪循環は避けたい。大人は憎まれ役を買って出て叱るべきです」(朝日新聞2016年9月28日朝刊)。
この中学生は叱らない教師に対して「もっと本気で叱って」と要求していますが、これは親にもそのままあてはまることです。
なんでもほめるばかりでは社会性が身につかず、自分の衝動をコントロールする力もつかないため、社会にうまく適応していくことができず、また思い通りにならない現実の荒波を力強く乗り越えていくたくましさも身につきません。それでは真の自己肯定感が高まるわけがありません。小学校高学年〜中学生くらいになれば、叱らずにほめてばかりの大人の姿勢に疑問を抱く子も出てくるのです。
結局のところ、自己肯定感は、けっしてほめることで高められるようなものではないのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

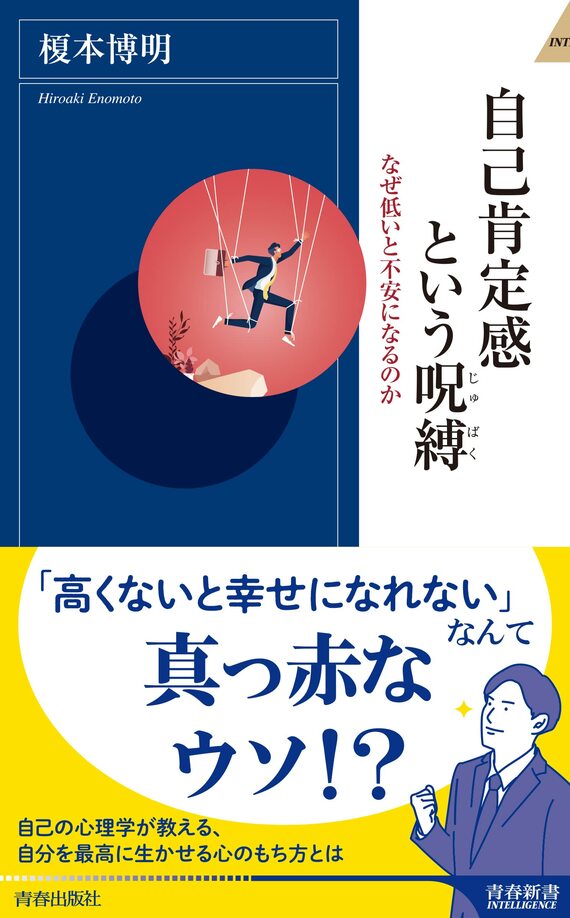






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら