さらに、文言をめぐってこの駆け引きが活発化しそうなところがある。それは、前掲の第3段落の、「アベノミクスの効果」で日本経済が「改善しつつあることを含めて」としたところである。
ここには、「アベノミクスの効果」として法人税収が上振れした分は、法人実効税率引下げの財源に充てたいという願望がうかがえる。そのうえで、「含めて」が、後ろの文言のどこにかかるのかが焦点となる。これが「恒久財源の確保をする」にかかるとみれば、法人税収が上振れたとしても恒久財源でなければ税率引下げ財源にはならない、と解釈されることとなる。
あるいは、「具体案を得る」にかかるとみれば、税率引下げ財源は恒久財源にこだわらず、財源に含められるとも解釈できるかもしれない。現時点で、筆者が知る限り、統一的な解釈があるとは聞いていない。そうだとすれば、年末までの税率引下げ財源の議論において、この文言の受け止め方をめぐる駆け引きが活発化するだろう。
法人減税は、経済成長や財政健全化実現の重要な一歩
以上が、「骨太の方針」における法人税改革をめぐる文言の背景である。「骨太の方針」だけをみるとこのようになっているが、同日に取りまとめた「日本再興戦略改訂2014-未来への挑戦-」や、27日に政府税制調査会で取りまとめた「法人税の改革について」も出されている。今後の法人減税の議論は、これらに盛り込まれた内容のうちどれを具体的に実行するかが焦点となる。
法人実効税率引下げの財源をどれにするかは、当連載の拙稿「本当に「法人税減税」はできるのか―改革の論点が、いよいよ出そろった」でも触れているが、政府税制調査会の「法人税の改革について」では、「法人税改革は、必ずしも単年度での税収中立である必要はない。また、法人税の枠内でのみ税収中立を図るのではなく、法人税の改革に関連し、他の税目についても見直しを行う必要がある。しかし、恒久減税である以上、恒久財源を用意することは鉄則である。」と明記されている。それだけに、恒久財源であることが強く意識されている。
今回の法人実効税率の引下げは、経済成長を促すためだけでなく、わが国の長期的な財政健全化を達成すべく、過度に法人課税に依存する税制から高齢化社会の中で安定的な財源となる消費課税へとシフトさせていくためにも、重要な第一歩である。年末の決着に向けて、しばらく「夏休み」に入るが、「秋の陣」での税制論議は是非有意義なものにしたいところである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

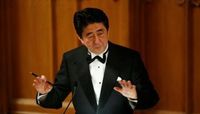





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら