「緊急事態宣言」が示す日本の法律の致命的欠点 想定外の緊急事態は「人の支配」に頼る危うさ

国家緊急権が悪用されたことへの嫌悪感が強い
日本において、なぜ緊急事態法制が整備されないのか。それは本格的に緊急事態の基本法を作ろうとすると、どうしても憲法の問題に行き当たり、強固な左右双方からのイデオロギーによって意見が発散して、議論がまともに成り立たなくなってしまうからだ。
日本の緊急事態法制において特別措置法(特措法)が多いのは、こうした本格的な憲法議論の「面倒くささ」を避けて、とにかくパッチワーク的に目の前の対症療法に終始してきたことの積み重ねの結果なのである。
これは戦前のような戒厳や緊急勅令に国家緊急権が悪用されたことへの反省がすぎるあまり、戦争やテロ、内乱のような政治性が強い緊急事態については、いまだに法制度を設けることへのアレルギーが強く存在しており、法整備にあたっての冷静な議論が成立しづらいという現状がある。
それでも大規模災害や新型インフルエンザのような政治性が薄いものは、比較的法整備が進めやすく、災害対策基本法や新型インフルエンザ対策特別措置法には、災害緊急事態の布告や緊急事態宣言が用意されている。
ところが、東日本大震災のような未曾有の大災害であっても、この布告は出されていない。その背景には、やはりかつての国家緊急権の発動に対する嫌悪感、忌避感が強く存在している。大仰なことをしてしまえば、野党やマスコミから批判を受けることが想定されるため、政府はできれば事を荒立てたくないのだ。
今回も新型インフルエンザ対策特別措置法の改正は議論にのぼったが、いったん感染拡大のスピードが落ちると、喉元過ぎれば熱さを忘れるとばかりに、議論が頓挫してしまう。



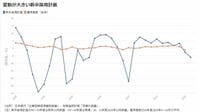



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら