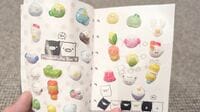共通テスト、新教科で浮上した「情報」って何? AIやITに欠かせないスキル「情報I」必履修に

30代以上のほとんどが「情報」を知らない!?
今、あなたの年齢はいくつですか? 「情報」という教科が、高校で学ぶ教科として設置されたのは2003年。だから、30代以上の方には、そもそも「情報」がどんな教科なのかについて説明をしなければならないだろう。
初めて高校の新教科として「情報」が登場したとき、「情報A」「情報B」「情報C」の3科目が選択必履修科目として設定された。このうちいずれかの単位を履修しなければ、高校を卒業できない単位になったわけだ。だが当時、多くの学校は「情報A」を設置して、基本的なPC操作としてWordやExcelの使い方を勉強させるのにとどまり、プログラミング学習などは積極的に行わなかったという。
では、最初に「情報」を学んだ子どもたちが高校を卒業する06年の大学入試に変化はあったのか。慶応の湘南藤沢キャンパス(以下、SFC)が「数学」でプログラミングの出題をし始めるなど、いくつかの大学の個別入試で「情報」の出題はあったものの、ごく少数の大学だったことから大きな影響はなかった。
その後、13年には学習指導要領が改定され、「情報」は「社会と情報」「情報の科学」の2科目選択必履修となるが、その教育を受けた子どもたちが卒業する16年に、SFCで初めて「情報」の入試が実施されたという。
これまで「情報」が入試の教科に入らなかった訳
「もちろん、その間『情報』を大学入試センター試験に加えることも検討されました。文部科学省など国も検討していたのですが、なかなか進まなかったのです」

情報処理学会理事、電子情報通信学会 「技術と社会・倫理」研究会副委員長なども務める
(提供:辰己氏)
こう話すのは放送大学教授の辰己丈夫氏だ。文部科学省の高大接続システム改革会議では、大学入学者選抜のあり方について、英語4技能試験や記述式問題の導入と併せて情報入試についても議論されてきた。内閣府でも、未来投資会議や統合イノベーション戦略推進会議などで情報入試の必要性が提言され、こうした動きと合わせて情報処理学会や大学入試センターなどの関連団体も情報入試について検討を重ねてきた。