京王と小田急、地形断面図でみる車窓の特徴 起点は同じ新宿でも「平坦」と「山あり谷あり」

京王線と小田急小田原線。起点は同じ新宿駅なのに、沿線の地形が両者で極端に異なっていることにお気づきだろうか。
京王は平坦、小田急は「山あり谷あり」
まずは新宿付近の地形を断面図で比べてみよう。京王線断面図(図1)が比較的フラットなのに対し、小田急線の断面図(図2)は山あり谷あり、変化に富んでいる。

京王線は新宿から下高井戸を経て府中の先まで20㎞以上、甲州街道に沿って敷かれている。後述するように甲州街道が比較的平坦なので京王線も平坦となる。

小田急は新宿を出ると代々木八幡まで標高差で約10m下った後、東北沢まで約15m上っていく。その先もジェットコースターのように上り下りを繰り返している。

なお線路は現在地下化や高架化が行われている。図は、線路がある位置の本来の地形である。敷設された時の地形といってもいい。
京王線にはこの区間で越える谷がないのに対し、小田急線は、代々木八幡付近で旧・宇田川(渋谷駅前を流れていた渋谷川の支流で現在は暗渠)、下北沢付近で旧・北沢川(目黒川の支流)など谷を次々に越える。
一方、江戸時代の人工水路である玉川上水、三田上水は、高い所(尾根)に造られていて、それらも横切っていく。現代の環七通りも尾根近くを通っているのがわかる。
新宿を出た小田急線は、代々木八幡付近で大きくカーブしながら丘を迂回するが、それ以後目の前に谷が現れようが丘が立ちはだかろうが、それらにひるむことなくほぼ真っすぐに郊外を目指していく。
幸い丘といってもさほど高くないので、トンネルを必要とすることはない。そのため断面図では山あり谷あり、線路は上りと下りを繰り返すわけである。なおこれは前述のように開業時の話で、現在は一部高架や地下となっている。













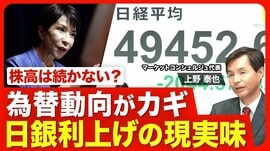
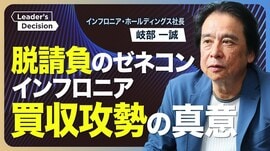






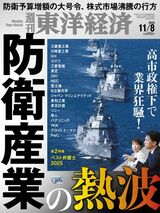









無料会員登録はこちら
ログインはこちら