日本人は地域のダークサイドに無関心すぎる 「悲しみの土地」を観光することで見えるもの
地域の悲しみの記憶は、実は隠すべき対象ではなく、潜在的に新しい価値を有している。そしてダークサイドの持つ価値は、これまで述べてきたように単に教訓にとどまらず、生き方の覚醒や社会構築といったレベルにまで多面的に波及する。こうした価値を重視した場合、「ダーク」という言葉を、お為(ため)ごかしのように明るい単語に無理に言い換えないほうが本質をつくこともわかる。ダークツーリズムに関する研究や旅行商品の開発は、決して地域に傷をつけるものではなく、地域に新しい価値を見出すための契機となるであろう。
ダークツーリズムから観る近代
また、筆者が研究を続けていくうちにわかってきたことであるが、ダークツーリズムの旅を続けることで、近代の構造が見えてくるという効用があった。これは複数の地域を巡ると腑に落ちてくると思う。
たとえば被爆地としてのヒロシマやナガサキで語り部の声を聞いたとしても、「お気の毒ですね」というレベルの共感と、核兵器に対する一方的な怒りしか湧いてこないのかもしれない。これ以前に、一般市民への無差別大量爆撃の前例としてはゲルニカの悲劇があり、日本人としては、(筆者はまだ赴いてはいないものの)中国が「無差別」と主張する重慶爆撃との共通点と相違点を考えるべきであろう。
さらに、核を肯定するテニアン島のエノラ・ゲイ出発地の記念碑やラスベガスの核実験博物館などの説明を通じて、マクロ的に「核というものはどういう意味を持っていたのか」という問いに対する多面的な歴史観が構築されてくる。換言すれば、国民全体が関わるようになった近代の戦争と、その帰結としての核の投下という事象に対して、一人ひとりが体系性を持った思いを語ることが可能になるのである。
これはある意味気楽な「旅人」だからこそ味わえる経験であり、1カ所に根を下ろして、その地と同化した場合は、距離を置いた体系性をとらえることが難しくなってくる。被爆者一人ひとりの体験も言葉も重いがゆえに、かえって全貌が見えにくくなるのである。
歴史家の山室信一が『キメラ──満洲国の肖像(増補版)』(中公新書)において「その時代を生きたということは必ずしも、その時代を総体として知っていたということを毫(ごう)も意味しない」と述べているとおり、個別の事象を体験された方の話はそれぞれ重要ではあるけれども、それだけでは歴史なり、社会なりの全体像を把握できないという問題は常に意識しておいたほうがよい。多くの情報を受け手側で集め、それを再構成することの意義がここでは説かれている。
そして、同書は別箇所で「空間そのもののありかたや空間認識という観点から人文・社会科学研究の再構築を図ることが、21世紀には緊要な課題として浮かび上がってきている」という問題提起を行っている。考察の対象を理解するためには、それがどの程度の距離なり、大きさなりを持っていたかということを知ることは非常に重要である。にもかかわらず、これまでの日本ではこうした直観的な感性に訴えかける研究方法はあまり顧みられることはなかった。ダークツーリズムが、非常に強力な分析のツールとなっているのは、訪問することによってこれまでないがしろにされてきた空間への理解が促進されるということも一つの理由ではないかと推察される。
悲しみの記憶を求めてさまざまな地を旅することで、「近代とは何か」という根源的問いに対するそれぞれの思いが湧き上がってくるであろう。これこそが、ダークツーリズムを体験することで得られる本質的価値の一つと言っていい。


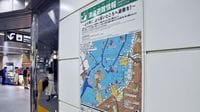































無料会員登録はこちら
ログインはこちら