外国人雇用の拡充は「無能な経営者」の甘えだ 生産性向上のチャンスを逃す「愚策」を許すな
先ほど、1975年から1995年までの20年間に零細企業が150万社も増えたと述べましたが、この間に増えたのは生産性が低い零細企業が大半でした。それと呼応するように、日本では1企業あたりの平均社員数も低下の一途をたどりました。

しかし、1987年あたりからは、1企業あたりの社員数が増加する傾向がみられます。企業の規模と生産性には強い相関関係が確認されているので、1企業あたりの社員数の増加は、日本経済がいい方向に向かっているサインだととらえることができます。
このように状況が好転したのは、経済における自動調整機能が働いたからにほかなりません。
労働人口が大きな企業に移りつつある
細かく見ていくと、さらに期待できる要素を見いだすことができます。

企業規模別のデータを見ると、企業規模によって雇用者数の増減率に違いがあることが確認できます。企業の規模が小さくなればなるほど、すなわち従業員の所得が少ない企業ほど、雇用者数が減少し、大企業、つまり所得の高い企業に人が集まる傾向が顕著に見られます。
統計上の平均賃金が上がっても、「上がっている実感がない」という声をよく耳にします。多くの人がそう感じるのは、平均給料があくまでも平均だからです。所得の低い企業から人が減ると、統計的な平均は上がります。自分の給料が上がらずに平均だけが上がりますので、実感が湧かないのは当然なのです。
なぜ小さい企業から人が減るのか。それは少子化により子どもの数が減り続けるからです。
1958年、日本では企業1社に対して3.1人の子どもが生まれました。一方、2015年はわずか0.28人です。これでは企業が人を雇いたくても雇えなくなるのは当然です。

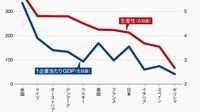
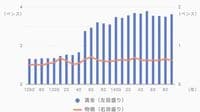




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら