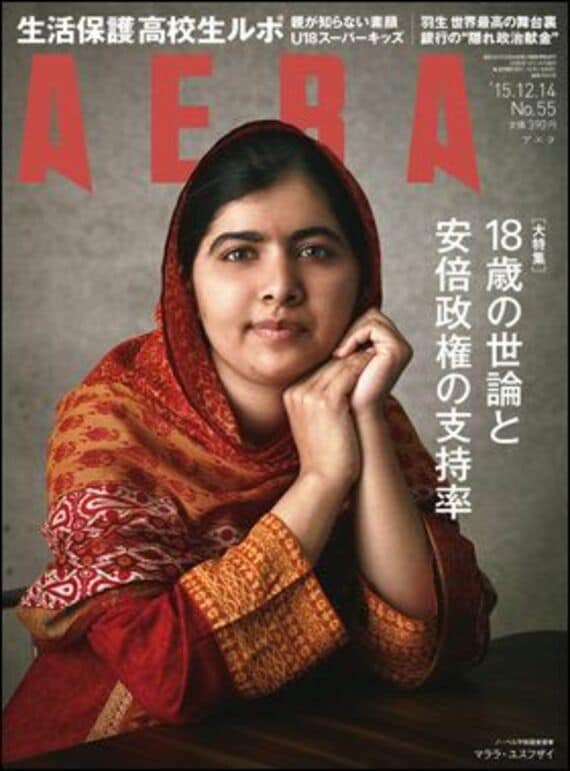圧倒的な絶望、「子どもの貧困」の現場を歩く 母を入院させ、僕はひとりになった

油のこびりついた台所。擦り切れたカーペット。古いアパートには隙間風も入る。
昨晩は毛布にくるまって眠ったんだ、と笑う啓太さん(仮名・19歳)は、夜間の定時制高校に通う4年生。生活保護を受けて、東京都板橋区のアパートで一人暮らしをしている。もともと母子家庭で2人暮らしだったが、母親が2年前、統合失調症で入院した。
母はパートを掛け持ちしながら啓太さんを育ててきた。忙しくて滅多に家にいなかったため、幼稚園から小学3年生まで、啓太さんに母と過ごした記憶はほとんどない。
生活保護費をやりくり

そんな母の異変に気づいたのは、小学4年生のときだ。具合が悪いと言って家にひきこもりがちになった。会話もかみ合わないことが増え、精神科への通院が始まった。
同時に啓太さんも学校に行かなくなった。勉強が嫌いなわけでも、いじめられていたわけでもない。初めてできた「母と一緒に過ごす時間」を大切にしたかったのかもしれない、と今になって思う。病院に付き添い、テレビゲームをして過ごす毎日。母は食事をつくることすら難しくなり、母の財布からお金を抜いて、コンビニでパンを買って食べることが多くなった。
不登校の背景に何があるのか。気づいてくれる大人は誰もいなかった。
心のバランスを崩した母と2人きりで過ごす時間は、嬉しいと同時に、どうしようもなく不安で怖かった。九州出身の母には身近に肉親もいない。自分がしっかりしなければと、小学6年のとき勇気を出して登校し、母の病気のことを担任の教師に相談した。返ってきたのは、思いも寄らない言葉だった。
「そんなこと言う暇があったら学校に来い」