
高市早苗首相が中国による台湾への海上封鎖などの事態において「存立危機事態になり得る」と答弁した11月7日以降、日中関係は悪化が続いている。中国側は強く反発し、外交部報道官や王毅外相が対日批判を展開、訪日旅行や留学への自粛要請、日本産海産物の輸入停止、日本文化関連イベントの中止など報復措置が続いている。
高市首相は、その後の国会答弁で「特定のケースを想定」した「明言」を今後は慎むと述べたが、撤回はしなかった。日本政府は答弁が2015年平和安全法制の枠内における一般論であり、対中関係の安定化努力を継続するとの姿勢を示したが、緊張は波紋として拡散した。
日本国内では「台湾有事は日本有事」という認識を当然視し高市発言を支持する論調と、憲法の専守防衛原則との整合性からの批判、さらには「台湾問題は中国の内政にもかかわらず、武力行使をちらつかせるのは有事を扇動している」という批判まで交錯した。高市氏の答弁の前後で日本政府の基本的立場に大きな変更はないものの、首相の言葉が直ちに「安全保障」の位相へと読み替えられ、国内外で情勢が緊張する構図となった。
筆者はこうした状況を「台湾有事」論の「安全保障化(securitization)」のプロセスであると見立てている。「安全保障化」とは、ある問題が「脅威」として提示される発話行為とその受容を通じて、政治的・社会的な課題が安全保障上の脅威として再定義されるプロセスを指す。「台湾有事」論をめぐる近年の動向で可視化されるのは、米中台そして日本をめぐる安全保障化の相互強化である。
「七十二年体制」の均衡が揺らぎだした
日本の台湾問題に対する基本線は、1972年の日中共同声明とその前後の国会答弁で定式化されてきた。中国の「台湾は中国領土の不可分の一部」という主張に対し、日本はこの立場を「理解し尊重」しつつ、ポツダム宣言第8項への言及を残し、台湾の独立を支持しない一方で最終的地位が未確定である現状をふまえた外交的妥協を形成した。
72年の政府統一見解(大平外相答弁)は、両岸の平和的解決を希求すること、平和的対話が続く限り「内政問題」として取り扱うこと、武力統一の可能性はないと考えていること(換言すれば武力統一時の対応は留保すること)、日米安保の運用は日中関係に配慮しつつ慎重に行うこと、という運用枠組みを具体化した。
台湾研究の先駆者である若林正丈・早稲田大学名誉教授は、この台湾海峡をめぐる国際的アレンジメントを、アメリカの「平和解決」原則と中国の「一つの中国」原則が交差する取り決めとして「七十二年体制」と名付けている。この体制の中で、日本政府はアメリカの「一つの中国政策」と整合し、中台間の問題の平和的解決を前提に、中国政府の「原則」を尊重しつつ台湾との非政府間の実務関係維持を柱にすえてきた。
ところが、2010年代後半以降、「七十二年体制」という半世紀近く続いた均衡は大きく揺らぎ、当事者がそれぞれの論理で動くことで相互のエスカレーションが常態化しつつある。台湾の清華大学栄誉講座教授を務める小笠原欣幸・東京外国語大学名誉教授は21年前後のこうした構造変化を「二十一年体制」と呼び、日米欧の緩やかな連携による対中抑止、国際空間での一定の台湾プレゼンス容認、中国の軍事的威嚇強化の3点をその特徴として指摘する。


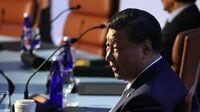































無料会員登録はこちら
ログインはこちら