同年2月のロシアによるウクライナ侵攻は「力による一方的な現状変更」の脅威を日本社会に現実のものとして突きつけ、日本の安全保障環境をめぐる脅威認識を大きく揺さぶった。さらに8月のペロシ下院議長訪台に対し、中国は日本のEEZ内に弾道ミサイルを初めて落下させる大規模軍事演習を行った。
これにより前年末に安倍元首相が言及した「台湾有事は日本有事」という認識が急速に日本社会に広まり、日本の安全保障政策は歴史的な転換点を迎えた。このような安全保障化の相互強化のスパイラルこそが、均衡点を七十二年体制の外側へ押し出す「二十一年体制」の実態である。
こうした中国による「台湾問題」の安全保障化とアメリカ側の対抗措置の連鎖は、1990年代にも先例がある。95年に台湾総統だった李登輝によるコーネル大学訪問に反発した中国は、翌96年の台湾初の総統直接選挙前にかけてミサイル実験や軍事演習を行った。これに対して、アメリカ側は空母2隻を台湾海峡に派遣して中国を牽制(第3次台湾海峡危機)。中国側の威嚇は結果的に高投票率での李登輝の圧勝と台湾社会における台湾アイデンティティーの強化をもたらした。
現状維持を「脅威」とする中国
第3次台湾海峡危機後の97年には米下院議長のギングリッチが北京訪問に続き台北を訪れ、台湾有事ではアメリカが防衛に動く姿勢を示している。当時と現在の違いは、このサイクルが単発的な危機ではなく、常態化しつつある点だ。
ここで重要なのは、中国が「脅威」として定義しているものの実態である。七十二年体制下では、台湾の民主的選挙や総統の訪米、日米台要人の往来などに対し、中国は反対しつつも軍事的・経済的威圧は一定程度抑制していた。
しかし、二十一年体制下では、こうした行為を「脅威」と位置づける法制度上の論理が体系化され、軍事演習の常態化や経済的威圧が恒常的手段へと転化している。現状維持を志向する台湾の民意や日米欧の関与そのものを安全保障上の「脅威」と定義し、非平和的手段を含む強硬な対抗措置を正当化する論理を固定化するものと言える。


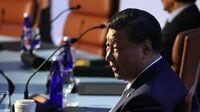





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら