「不登校35万人超」過去最多、調査結果に表れない「出席扱いの子」の実態は把握できているか? 「"学びの多様化学校"の設置だけでは限界」の訳
つまり、何か1つの手段や方法で不登校対策をするのではなく、複層的な支援が重要かつ有効であるということ。そして、そこで必要なのは、「授業に出たい」「将来を目指して頑張りたい」という、学びに向かう気持ちの醸成だ。
ポイントは、安全安心の提供と1人ひとりへのエンパワーメントである。寄り添うさまざまな大人が、児童生徒が自身の「好きなこと」から 「やりたいこと/なりたいこと」が見つかるよう支援していくことで、児童生徒自らが将来の希望や進むべき道を見つけていくことができる。
不登校状態の児童生徒は好きなことを見つけることすら大変だが、多くの大人や友人と関係を作りながら少しずつでも“好き”を“目標”に変えることができれば、徐々に登校への意欲、生きる自信を取り戻していけると考える。
「学びの多様化学校」の設置だけでは限界がある
文科省のCOCOLOプランでは、学びの多様化学校を全国に300校設置することを目標に掲げている。筆者は高尾山学園の校長を務めた12年間に500名以上の生徒を送り出してきた経験から、教職員の体制も手厚い学びの多様化学校は不登校対策の有効な手段であると考える。
しかし、いくら全国に設置が進んだとしても、35万人超の不登校児童生徒に対応するには限界があるとも思っている。
そもそも通常校で不登校の児童生徒を生み出さないようにすることが最優先であり、「授業が楽しい」「学校に行きたい」「友達と一緒に活動したい」「信頼できる先生がいる」という気持ちを育めるような学校づくりが求められる。
そのためには学びの多様化学校を中核として、まずは不登校児童生徒の対応に優れた教職員の育成を図ると共に、設置された行政区内のすべての通常校の教職員を対象に座学だけではなく学びの多様化学校での実地研修を行い、不登校対応のノウハウの習得と教員自身のマインドを高めていくことが必要だろう。
さらに、教員養成系の大学とも連携してゼミを学びの多様化学校内に置くなどして、レベルの高い不登校への対応力を教員が身に付けることが、不登校対策の次の一手になると考える。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

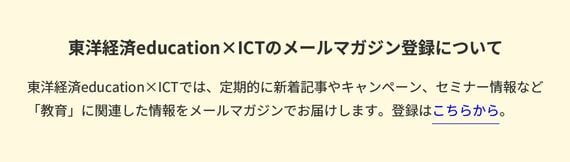































無料会員登録はこちら
ログインはこちら