【前編】板橋区とスダチの騒動で炎上「不登校ビジネス」何が問題視されたのか 「わらにもすがる思い」孤立し不安に陥る保護者

板橋区での騒動を機に広がる「不登校ビジネス」の議論
まずは、不登校ビジネスがSNSやメディアで盛んに取り上げられるようになった経緯について、おさらいしよう。事の始まりは、2024年8月5日、民間事業者のスダチが「板橋区と連携し、区内の特定の小学校を対象に、スダチが展開するオンライン再登校支援を実施する」と発表したことにある。同社はこれまで自社のHPで「不登校を3週間で解決する」とうたい、不登校の子を持つ保護者に再登校支援サービスを提供してきた事業者だ。
同社の発表後、SNSでは賛否両論が飛び交う事態に。当初は「一部の学校で試行を始めた」と認めていた板橋区教育委員会も、批判の高まりを受けて「そうした事実はない」と否定に転じた。スダチもまたプレスリリースを削除。連携は白紙となった。
一方8月15日には、この一件を重く見た不登校支援関連の市民団体や有識者などが、連名で板橋区に公開質問状を提出。同区は、9月に区HPと公開質問状への回答を通じて、スダチとの一連の経緯についての説明と、「『学校に登校する』という結果のみを目標としない」等の従来の区の不登校方針が変わらないことを公表した。
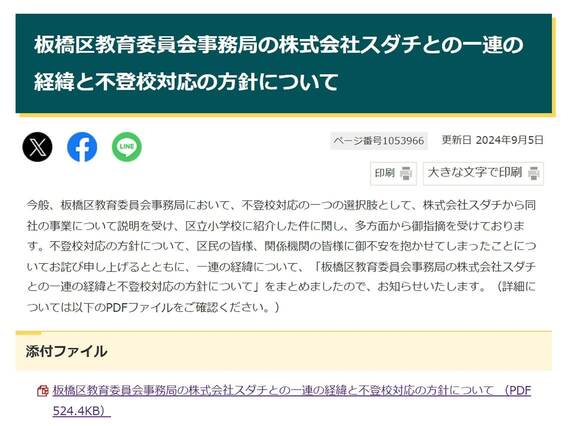
(写真:板橋区HPより)
しかし、騒動は収束した形となったものの、これを機に不登校ビジネスの是非を問う議論が広がり、今もなお教育界や社会全体に波紋を投げかけているのだ。
今回の騒動でクローズアップされたのはスダチだが、再登校支援のサービスを提供する事業者はほかにも複数存在する。なぜこうした不登校ビジネスが、問題視されたのか。
「『再登校を目指す』という選択肢を当たり前にすること」
これまでのスダチのHPやプレスリリース、代表の小川涼太郎氏の著書などを見てみると、まず同社は「不登校に悩むご家族やお子様にとって『再登校を目指す』という選択肢を当たり前にすること」を目標に掲げてきた※。実際に2020年7月にサービスを始めてから、1300人以上の子どもが再登校を実現しており、支援開始から再登校までの日数は平均17日、再登校できた子どもは90%以上に達するという。
※現在、スダチのHPでは「再登校をゴールとしていません」と表現している

(写真:スダチHP<2024年9月時点>より)
また、不登校を「学校」と「家庭」の2軸で捉えており、どちらかの状況がよければ子どもはつらさを乗り越えて学校に行くことができると考えている。ただし、学校の状況を変えるのは容易ではない。そこで家庭の状況を変えることにアプローチしていくというのが、スダチのスタンスだ。






























