働き方改革で注目の元教頭、いかに根強い「教員の固定観念」変えたのか 中村浩二校長「教員が探究的に働ける仕組みへ」

教員の心に寄り添い「適応課題」に対応することが重要
「今の働き方では、教員の生活も学校自体も持続可能ではなくなってしまいます。教育を大切にしない国はやがて滅びます。文部科学省には教育に関わる予算や人を潤沢に割いていただき、教員が生き生きと働き、子どもたちも楽しいと思って通えるような学校の環境を整えていただきたいと強く願っています」

名古屋市立豊田小学校校長
1970年愛知県名古屋市生まれ。愛知教育大学教育学部理科生物学教室卒。93年より名古屋市立小学校教員。2010・11年度、愛知教育大学教育実践研究科(教職大学院)学校づくり履修モデルへ派遣され、学校評価のあり方を中心に学校運営について学ぶ。17年度より名古屋市立東築地小学校教頭、19年度より名古屋市立矢田小学校教頭、22年度より現職。「学校の働き方改革」「組織開発」に関する講演多数、著書に『全職員が定時で帰る スクールリーダーの職員室革命』(明治図書)。日本教育経営学会所属。2児の父
そう語るのは、名古屋市立豊田小学校で校長を務める中村浩二氏。自らも教頭時代に働き方改革に尽力してきた。40代の頃に教務主任になってから、学校運営や組織開発について学ぶようになったというが、それが中村氏の改革の土台になっている。
組織開発には、組織の課題を「技術的問題」と「適応課題」に分けて捉える考え方がある。技術的問題とは、スキルや仕組み、テクノロジーの導入などで解決できる問題のこと。一方、適応課題は、当事者の意識や行動が変わらないと解決できないような問題を指す。
中村氏は、勤務時間外在校時間の縮減を目指すうえで数多くの技術的問題の解決に取り組んできたが、併せて重要なのが「教員の心に寄り添いながら適応課題にアプローチをしていくこと」だと語る。
前任の2校とも、当初は「学校や教員はかくあるべきという固定観念が非常に強くあった」(中村氏)という。例えば、下校時間の繰り上げを提案すると「下校後に地域で問題が起こった際、学校は対応しなくていいのか」といった意見が出る。当時はまだ民間委託されていなかった部活動の時間制限についても、その指導を熱心に行う教員から疑問の声が上がった。
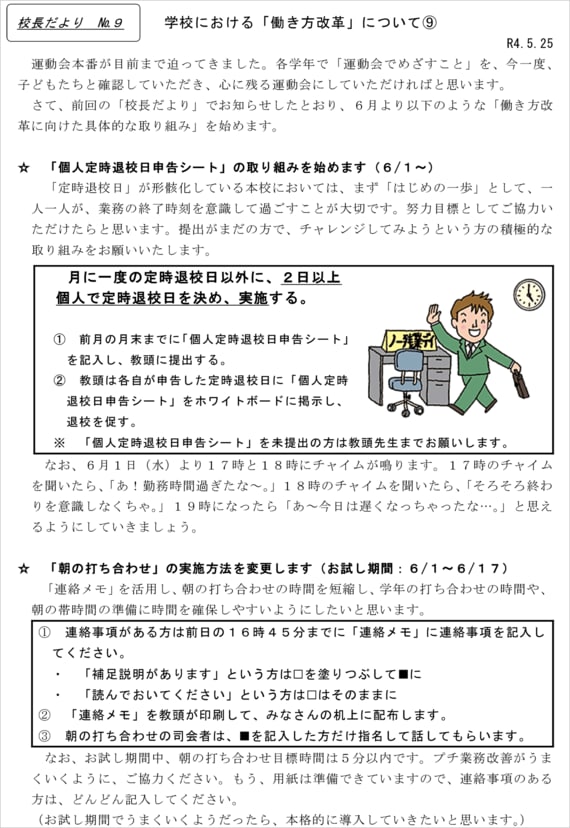
今年度も「校長だより」を発行している
「勤務時間外在校時間の縮減は今までの働き方が否定されるようなもので、教員は受け入れがたいわけです。なので、なぜ働き方改革が必要か、ワーク・ライフ・バランスの本来の意味は何か、今の働き方は持続可能かといったことを教員向けに『教頭だより』を作って発信するなど、意識を耕すことから始めました。振り返ると、ここが最も働き方改革において大事な部分だったと思います」
































