したがって、懲戒処分を行う際、その処分の妥当性の担保は重要です。
ハラスメントの行為者であっても、自社の従業員を正当な手続きなく懲戒処分したり、重すぎる懲戒処分をすれば、企業は懲戒処分権の濫用として「無効」になってしまう恐れがあるのです。
被害を受けた労働者への心情に配慮しつつ、当事者に適当な懲戒処分を行うことを考えると、企業の負担は非常に大きなものになるでしょう。
処分の判断基準
適当な処分の判断基準として、次のような考え方が用いられます。
・ 過去、類似の事件があったときに科した社内の懲戒処分の履歴
・ 過去、類似の事件に対する裁判所の判断
・ 弁明の機会を付与して聴取・考慮した本人の言い分
こうした点からも、類似の事例を知ることはとても重要です。
自分が被害者になった場合、加害行為をした者に対して会社がどのような対応をしそうかが予測できますし、どのような場合に加害者になり得るのかを理解することは、当事者として自身を守ることになります。
また、企業も他社事例を知ることで、自社の労働者がハラスメントにあたるような言動を行っていた場合の懲戒処分を適切に行うことができます。
加えて、処分の難しさを考えても、やはりハラスメントが起こらない職場づくりを進めることが重要になります。
●ハラスメントがあったかどうかの判断基準は、一般常識を基準に考えて問題ない
●ハラスメント行為者に対する企業側の懲戒処分は、一般的な感覚に比べるとかなり軽く、慎重になされていることが多い
●適切な懲戒処分を行うために他社の状況を知ることも重要だが、そもそもハラスメントが起こらないような職場づくりも大切である
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

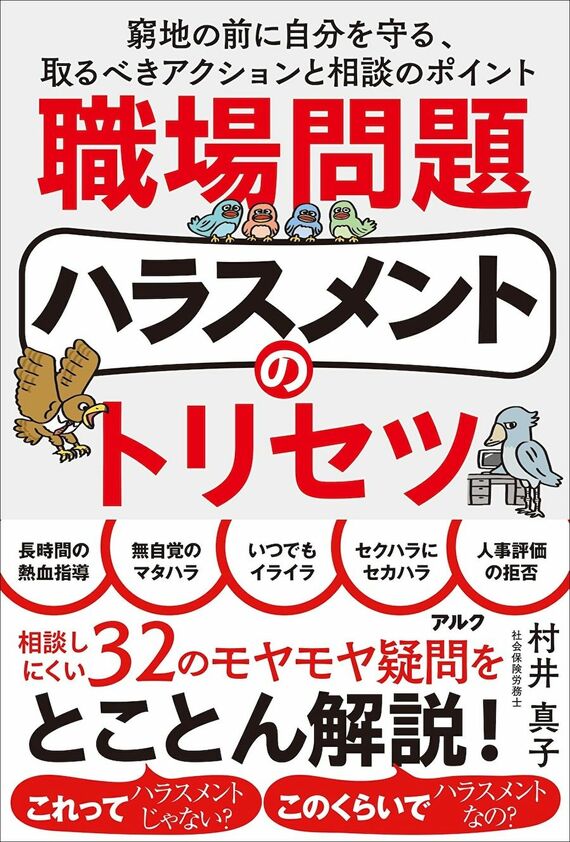






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら