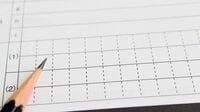子どもの学力低下、背景は複雑?コロナ禍、保護者の変化、測る指標が「古い」説も 学習指導要領が変わっても同じ指標でいいのか
まず、今年の調査の対象となった小学6年と中学3年であるが、ともに重要な時期をコロナ禍で数年間の学校生活を過ごしている。従来では考えもつかなかった家庭での学習(一部オンラインでの授業)が行われた。登校しても「密」を避けることが推奨され、授業での発言も控え、行事も大幅に縮小されてしまった。
「指導」という教師がある方向に向けて生徒を引っ張っていくという言い方は、個人としては好きではないが、現場からすると明らかにこの時期は学習指導の時間が不足し、子どもたちの学習習慣がつきにくかったと考えられる。コロナ禍の影響で学力が低下したのは相関関係があるのだろう。
違う観点からも考えてみる。保護者の意識の変化だ。少子化は進行し、その理由もあって受験の形態は変化している。
近年、大学受験においてはいわゆる年内入試(学校推薦型選抜、総合型選抜)の割合が増加して過半数を超えるようになってきた。ペーパーテストが求められない選抜方法も一般的になっている。
また、多くの子どもたちにとって人生の第一関門ともいえる高校入試も推薦入試や特色選抜など、学力検査以外の入試が多様化している。保護者からすれば、無理に頑張らせなくても、受験はそれなりになんとかなるものになってしまった。
「今しっかりと勉強しておかないと後々後悔するよ」という以前のようなお説教は、正直あまり聞かれなくなったといえる。
一方、首都圏では中学受験が過熱化した状況はまだまだ続いており、学歴や学習歴にこだわる保護者層がいるのも事実である。学力に関して、調査結果からも世の中が二極化していることが見て取れるのではないだろうか。
新学習指導要領とGIGAスクール構想の狭間で
一方、教える側の変化をコロナ禍前後で考察してみる。
実は、コロナ禍は新学習指導要領が施行された時期と重なっている。この10年くらい前からブームになったアクティブラーニングの流れの中で、「主体的で対話的な学び」が新学習指導要領の1つの柱になっているが、コロナ禍の制約の中でどのように教育に取り込んでいくかは、多くの教師にとって一苦労だったはずだ。
またGIGAスクール構想の「一人一台端末」がコロナ禍のおかげで加速的に進み、現場で使い方の共通理解が不十分なまま、子どもたちのデジタルでの学習が一気にスタートすることになった。