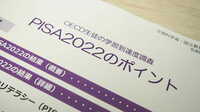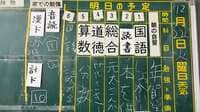2024年度「全国学力・学習状況調査」、算数は立体図形に関する知識の活用に課題 授業改善や指導方法改善の方向性の手がかりに

全国学力・学習状況調査の目的と、調査から得られる結果の活用
全国学力・学習状況調査(以下、全国学調)は、日本の教育の現状を明らかにし、教育政策や授業改善に具体的な方向性を示す取り組みの一環として行われている。教科に関する調査問題の作成・分析は国立教育政策研究所(以下、国研)が主体となり、文部科学省と連携して進められている。国研教育課程研究センター長の大金伸光氏は、その意義について次のように語る。
「全国学調の目的は、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図ることです。児童生徒の学力や学習状況を把握し、教育政策の成果や課題を検証することが主な役割となっています。また、学校現場に調査結果をフィードバックし、授業改善につなげることも重要です」
全国学調は、学力のアセスメントとしての機能だけでなく、教育施策や学校現場での指導改善に寄与するための情報提供ツールとしての役割を持つ。この調査が実施される背景には、義務教育の水準維持と、全国的な教育の機会均等の実現という課題がある。
全国学調では、国語や算数・数学などの教科調査が実施され、そこから得られた結果と分析が教育現場で活用されている。それぞれの教科において、得られた知見は実践的な授業改善の指針となっている。
なお、正答率だけでなく、誤答や無回答の状況を総合的に分析し、課題を評価している点も特徴だ。正答率が高くても誤答を類型に分けて分析することで、理解の深さや指導の課題が明らかになる。
また、無回答率が高い場合、児童生徒のつまづきが明らかになるような設問の工夫が求められる。こうしたデータに基づき、教育現場は授業改善や指導方法の具体的な改善点を見出す手がかりを得ている。
各教科の現状と課題。調査結果から見えてくるもの
2024年度の調査では、国・公・私立学校の小学校6年生、中学校3年生を対象に、国語と算数・数学の教科調査が行われた。どのような特徴が見られたのか、教科ごとに詳しく見ていこう。
国語
2024年度の国語の調査では、児童生徒が目的に応じて情報を取り出すことや、事実と意見を区別して表現することに課題を抱えていることが明らかになった。具体的には、取材メモを基に自分の考えを文章にまとめる問題では、事実を並べるだけで、自分の意見として論理的に展開することができていない児童が散見された。