日本「PISA2022」3分野すべてで世界トップレベルの真因、読解力は2位に急上昇 国立教育政策研究所・大野彰子氏に聞いた
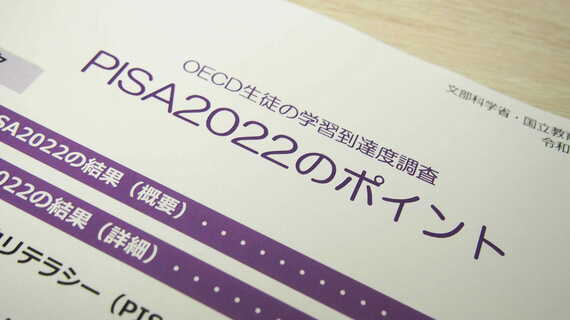
3分野すべてにおいて「世界トップレベル」その要因とは
──OECDが進める国際的な生徒の学習到達度調査「PISA2022」が2023年12月に発表され、日本は、OECD加盟国37カ国中「数学的リテラシー」1位、「読解力」2位、「科学的リテラシー」1位と3分野すべてにおいて世界トップレベルという結果でした。中でも「読解力」は、前回の11位から2位に急上昇しています。この要因について教えてください。

文部科学省 国立教育政策研究所 教育データサイエンスセンター長(併)国際研究・協力部長
1994年文部省(現・文部科学省)入省。アメリカ留学(コロンビア大学大学院)、岡山県教育庁生涯学習課長、文科省高等教育局国立大学法人支援課課長補佐、OECD教育局アナリスト、カンボジア教育省教育計画アドバイザー(JICA専門家)、文化庁長官官房国際課長、同文化財第二課長、文科省大臣官房総務課広報室長、同総合教育政策局調査企画課長等を経て、2022年4月より現職
(写真:本人提供)
大前提として、このような調査結果は順位など「数字」のほうに焦点があたって一喜一憂しがちですが、「結果をどう捉え、今後の教育現場にどう落とし込んでいくか考えていくための1つの指針」として受け止めていただきたいと思います。
それを踏まえたうえで申し上げると、「PISA2022」では、日本は数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー3分野すべてで世界トップレベルという結果が出ました。また、前回の2018年調査から、OECDの平均得点は低下した一方、日本は3分野すべてにおいて平均得点が上昇したこともわかりました。
この要因の1つとして、日本は新型コロナウイルス感染症のため休校した期間が他国と比べて短かったことが影響した可能性があることが、OECDから指摘されています。このほか、学校現場において現行の学習指導要領を踏まえた授業改善が進んだこと、PISAはCBT(コンピューター使用型調査)による調査なのですが、GIGAスクール構想前倒しによりICT環境の整備が進み、生徒が学校でのICT機器の使用に慣れたことなども考えられています。
読解力の上昇に関しては、全国学力・学習状況調査の結果や現行の学習指導要領等を踏まえ、各学校において児童生徒の言語能力の確実な育成に向けて教科等横断的に取り組んできたことが功を奏したという見方もできます。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら