「なんとなく」は通用しない、国語が伸びない子に効く東大生"対話式"の学習法とルール4つ 大人先攻、会話量「1:1」で思考過程を引き出す
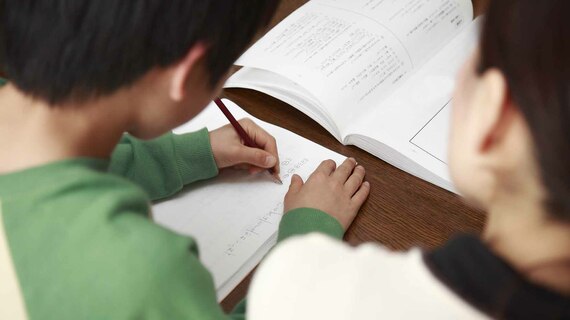
「なんとなく」のまま教えられてきた国語
子どもが国語のテストを受けたとき、こんなふうに聞かれたことがあるかもしれない。
「なんでこの答えじゃダメなの?」「自分の答えのどこが悪いか分からない」ーー
あなたはそのとき、「なんとなく」や「そういうものだから」以上の返しをすることができただろうか?

1998年生まれ。中学生のときに東大を目指すことを決め、定時制高校にも塾にも通わず、通信制のNHK学園を経て、独学で2018年東京大学文科Ⅰ類合格(2次試験は首席合格者と3点差で合格)。東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、2023年に東大生がつくる国語特化のオンライン個別指導「ヨミサマ。」を立ち上げる。現在、東大生講師150名、生徒数は900名(延べ)を超える規模に成長。著書に自分自身の独学ノウハウを詰め込んだ『成績アップは「国語」で決まる!』がある(X:@Kanda_Overfocus)
(写真は本人提供)
国語の成績が伸び悩む子どもたちに共通する特徴がある。それは、国語の問題を「なんとなく」で解き続けていることだ。その陰には当然、大人たちが「なんとなく」国語を教えてきた現実がある。
日本の学校教育では、正しい文章の読み方を学ぶことが少なく、特に教える側が国語を得意としていた場合ほど、子どもが「なぜ国語で点数を取れないのか」を理解するのが難しい。
しかし現在、教育改革や中学受験の過熱によって、読解力や思考力が問われる入試問題が増えてきた。そのため、“雰囲気で挑む”国語ではもはや太刀打ちできない時代が到来しようとしているのだ。
国語(現代文)という科目は、他科目と比較して暗記の要素が極端に少なく、考える道筋や正解が明確に説明されにくいという特徴を持つ。
そのため、国語の問題は「なぜ自分の答えが間違いなのか」「どのように考えれば正解に至るのか」が分からないまま終わってしまいがちだ。とはいえ、今後同じ題材が出るわけでもないため、「まあいいか」とそのままにした経験がある人も多いかもしれない。実は私も、小中学生はまさにその1人だった。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら