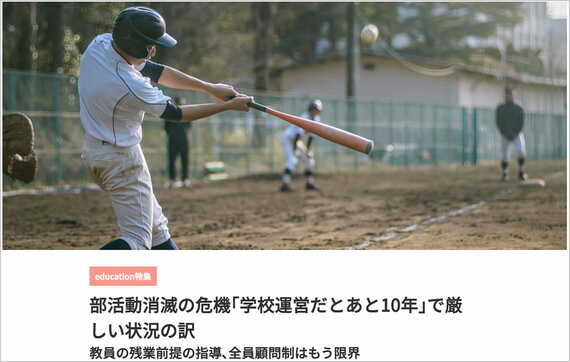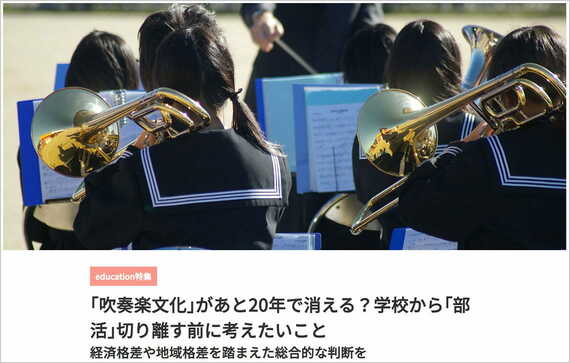学校教育関係者向け、2022年がよくわかる「最も読まれた記事」トップ10 部活動の地域移行、教員不足、働き方改革ほか

「1人1台端末」の整備で授業の形も変わらなければならない
新型コロナウイルスの感染拡大により3年も前倒しされたGIGAスクール構想。「まずは使ってみる」といったように、走りながら「1人1台端末」の活用を進めてきたというところも多いだろう。
そんな中「デジタルの学びとは何か」「デジタルの学びで何ができるのか」、いったん立ち止まる必要性を訴えるのが、熊本市教育センター主任指導主事(取材当時)の前田康裕氏だ。前田氏に取材した「自ら学ぶ力が育たぬ『教師が教える授業』を脱すべき本当の理由」は、端末の活用を扱った記事の中で、今年最も読まれた記事だ。
教師が教える授業から、子どもたちが学び取る授業に転換する必要性について、前田氏の著書から漫画も抜粋しながらわかりやすく解説する。
部活動消滅の危機にどう対応するか
学校の部活動が、こんなにも注目された年は、これまでになかったと言っても過言ではないだろう。
今、中学校などの部活動を学校単位の活動から地域単位の活動に移行するための準備が加速している。運動部はスポーツ庁で、文化部は文化庁で、それぞれ有識者会議で検討が進み、休日の部活動から段階的に地域移行していく方向にある。
部活動改革の背景には、少子化に伴って学校単位での部活動の維持が困難になっていること、そして指導する教員の負担軽減という働き方改革の2つがある。
こうした中で、「改革仕掛人」として部活動の現場を見つめ続けてきた学習院大学教授(取材当時)の長沼豊氏に取材した「部活動消滅の危機『学校運営だとあと10年』で厳しい状況の訳」では、運動部を中心に部活動の現状と問題点、今後のあり方についてひもといた。
学校から「部活」を切り離す前に考えたいこと
だが部活動は、誰もがスポーツを、また文化芸術を等しく体験できる機会でもあり、よりよい形で存続するためには何が必要なのかは十分な議論が必要だ。
さらに文化部には、運動部とはまた異なった事情がある。中でも吹奏楽部は、比較的練習時間が長いといわれ、教員の長時間労働や生徒の学業との両立問題が指摘されることも多い。
そこで、文化庁「文化部活動の地域移行に関する検討会議」の委員であり、一般社団法人全日本吹奏楽連盟理事長の石津谷治法氏と、『日本の学校吹奏楽を科学する!』の著者である愛知教育大学教授の新山王政和氏の対談を実施。議論が白熱して長時間にわたる取材だったが、「『吹奏楽文化』があと20年で消える?学校から『部活』切り離す前に考えたいこと」は公開直後から多方面で読まれ、さまざまな反響があった。
本当に学校から切り離せるのか、部活動の受け皿、指導人材をどう確保するのかなど課題は多く、各自治体で持続可能な部活動のあり方について模索する動きが今後加速していくだろう。
教員の業務が膨れ上がる中、長時間労働の是正をどう進めるか
部活動改革なくして、学校の働き方改革は実現しないといわれるものの、地道な努力の積み重ねで勤務時間の削減に取り組む学校もある。