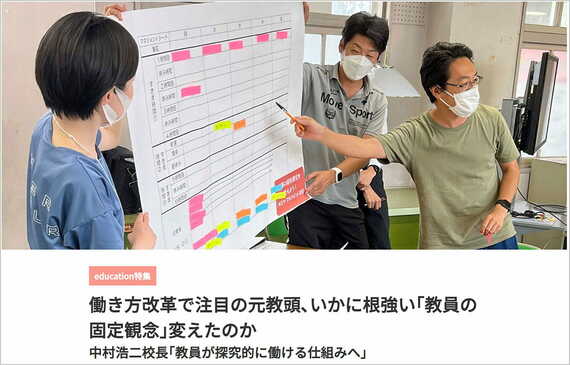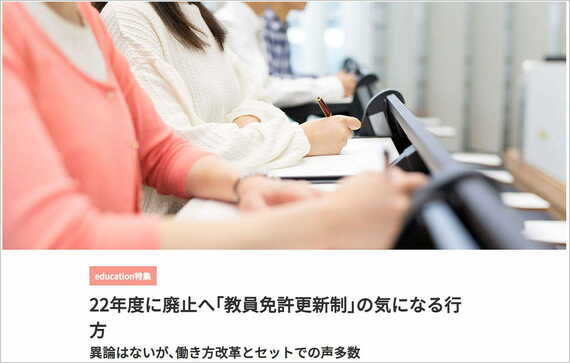学校教育関係者向け、2022年がよくわかる「最も読まれた記事」トップ10 部活動の地域移行、教員不足、働き方改革ほか
名古屋市立豊田小学校で校長を務める中村浩二氏は、教頭時代、校長の指導を受けながら職員と協力して働き方改革を推進。前々任校では過労死ラインとなる月80時間以上の勤務時間外在校者ゼロ、前任校では1カ月当たり1人平均で最大約10時間の勤務時間外在校時間の縮減という成果を出してきた。
こうした中村氏の取り組みを取材した「働き方改革で注目の元教頭、いかに根強い『教員の固定観念』変えたのか」は、記事の公開から半年経った今も継続して読まれている。何かをやれば働き方が劇的に改善するといったことはなかなか難しいが、1つずつ着実に取り組むことが成果に結び付いている好例だ。
学校事務職員という立場から働き方改革を推進
一方、学校事務職員という立場から働き方改革を推進しようと奮起する人もいる。横浜市立日枝小学校の学校事務職員・上部充敬氏だ。
上部氏は「職員室を中心とした『働く場改革』から『働き方改革へ』」「(職員室の)環境が変われば意識が変わる。意識が変われば働き方が変わる」をモットーに、働きやすい職場づくりに取り組んできた。
「職員室のリノベーションで『働き方が変わる』学校事務職員の知られざる底力」では、職員室のリノベーションの視点から教職員の人間関係を良好にし、生産性を高めるマインドやノウハウをまとめている。
新学習指導要領の新しい評価の規準「3観点」
22年の教育界を振り返ったとき、高等学校の新学習指導要領が4月にスタートしたことは、やはり大きなトピックだったといえるだろう。20年度に小学校、21年度に中学校と順次実施されてきたわけだが、高校では情報Iだったり、歴史総合だったりと大きな変更があった。
これに合わせて見直された評価の規準が、いわゆる「新しい3観点」だ。先生方の関心が非常に高いため継続して記事を出しているが、國學院大學教授の田村学氏に取材した「新学習指導要領の『3観点』正しい評価3つの方法」は、いちばん読まれた記事だ。改訂の狙いやメリット、評価の注意点などについて詳しくまとまっているため、ぜひ確認してみてほしい。
「教員免許更新制」廃止後の研修制度はどうなるか
そして22年7月には、小・中学校、高等学校校の教員などを対象に10年ごとの講習を義務づけていた「教員免許更新制」が廃止された。
「多忙な教員にとって30時間確保するのは負担が大きい」「ただでさえ勤務時間内に仕事を終わらせることができないのに、外部に研修に行くのは大変」「実践的ではなく現場で役立っていない」など負担感が大きかったため、業務が膨れ上がる一方の現場からは好意的に受け止められた出来事だった。しかし、廃止後に新たな研修制度、またその受講履歴が記録されるとあって現場からは同時に不安の声も聞かれる。
「22年度に廃止へ『教員免許更新制』の気になる行方」は、廃止の方向が決まり早々に公開した記事だが、中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在り方特別部会・教員免許更新制小委員会」の委員で、学校関係職員への研修などを行う独立行政法人教職員支援機構 理事長の荒瀬克己氏に取材したもので、この1年を通じてよく読まれている。新しい制度の狙いも含めて確認できる内容になっている。
学校から悲鳴、教員不足が社会問題化
文部科学省が22年1月に公表した「全国の公立学校1897校で、2558人もの教員が不足している」(21年4月1日時点)という調査結果は、学校現場のみならず社会に大きな衝撃を与えた。