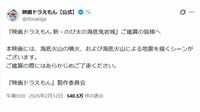22年度に廃止へ「教員免許更新制」の気になる行方 異論はないが、働き方改革とセットでの声多数

不満の声が絶えない教員免許更新制が廃止へ
教員免許更新制とは、小中高校の教員などを対象に10年ごとの講習を義務づけ、講習を受けなければ教員免許状が失効してしまう制度。定期的に講習を通じて最新の知識技能を身に付けることで教員として必要な資質能力を保つために、2007年の改正教育職員免許法の成立を経て、09年から実施されている。
09年4月1日以降に授与された教員免許状には10年間の有効期間があり、原則として有効期間満了日の2年2カ月から2カ月前までの2年間のうちに、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講しなければならない(09年3月31日以前に授与された旧免許状に有効期間はないが、生年月日によって割り振られた期限までに講習を受講しなければならない)。費用の約3万円は自己負担で、休日や夏休みなどを利用して受講する必要があることなどから、不満の声が絶えなかった。
「多忙な教員にとって30時間確保するのは負担が大きい」「ただでさえ勤務時間内に仕事を終わらせることができないのに、外部に研修に行くのは大変」「講習の内容が今の時代に合わない」「実践的ではなく現場で役立っていない」「教員免許制度そのものが複雑でわかりにくい」「弁護士も医師も免許は終身制なのに、なぜ教員だけが更新制なのか」など。学校現場の負担感に加えて、グローバル化や情報化の進展で目まぐるしく変化する社会との乖離も、制度導入から10年以上が経って目立ち始めていた。
さらに更新期限を忘れて失職する「うっかり失効」が相次いだり、休職中の教員が復帰する足かせになったり、定年間近の教員が更新のタイミングで早期退職したりするなど、学校現場の人手不足に拍車をかける要因にもなっていた。
そんな教員免許更新制が22年度にも、廃止になりそうだ。廃止するには法改正が必要だが、文部科学省は今年の通常国会で法改正を成立させ、22年度の早期に廃止し、23年度からは新しい制度を始める方針。現状では未定だが、22年度末に期限を迎える教員は、更新が不要となる可能性がある。
「発展的解消」の中身、新たな教師の学びのあり方とは
ただ、文科省は教員免許更新制の「廃止」ではなく、あくまで「発展的解消」と表現している。教員免許更新時の講習に代わる新たな教師の学びのあり方を検討しているからだ。いったいどんな制度になるのか。
「まずは働き方改革に取り組んでほしい」「教職員数を増やしてほしい」「現場の声を聞いて真に役に立つ制度にしてほしい」など、早くも現場からは不安の声が聞こえてくる一方で、「教師が学び続けることに異論はない」「余裕ができれば自分で必要な学びに取り組む」といった前向きな声も多い。
教員免許更新制の抜本的な見直しを含む、教師の養成・採用・研修のあり方について検討してきた中教審の「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在り方特別部会・教員免許更新制小委員会」の委員で、これまで学校関係職員への研修や、教員の資質能力向上に関する調査研究を行ってきた独立行政法人教職員支援機構 理事長の荒瀬克己氏は、こう話す。
「いちばん大きな問題点は、講習が教員免許にひも付けされていたことです。教員免許更新制に関係なく、教員は学び続けなくてはなりません。学習指導要領の冒頭に、『主体的・対話的で深い学びの実現』とありますが、これは児童・生徒だけではなく先生にも当てはまるものです。自分に何が足りないのか、何の力をつけなければならないのか、主体性を持って学んでほしいと考えています」