学校の課題を解決するヒントに!年末年始に読みたい「教育書」厳選10冊 日常とは違った視点で課題を読み解く読書の力
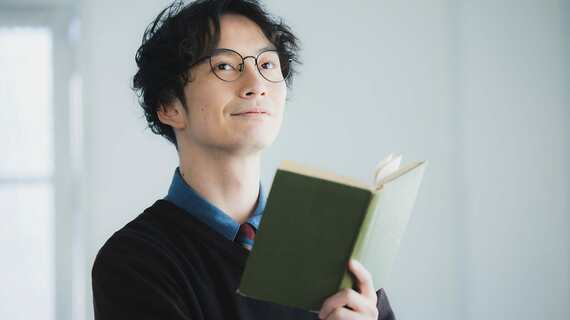
「叱らない」が子どもを苦しめる(著:藪下遊ほか)
小・中学校の不登校は11年連続で増加し、34万6482人と過去最多となった(文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)。
文科省は、不登校の子の支援について「登校するという結果のみを目標としない」ことを明言しているが、「登校を促さない」アプローチが効果を上げる一方、それだけでは状況が改善しないケースもある。
『「叱らない」が子どもを苦しめる』(ちくまプリマー新書)は、現役のスクールカウンセラーがこうした状況に警鐘を鳴らしている。石川県内の小・中・高でスクールカウンセラー、福井県総合教育研究所で学校では対応が難しいケースや緊急支援などを担当する藪下遊氏と、和光大学 現代人間学部教授 髙坂康雅氏の共著だ。
藪下氏には、こちらの記事「葛藤を通した成長が大切、『登校を促さない』で改善しない不登校の子への対処」でも話を聞いているが、この本には不登校の子を取り巻く社会や学校、家庭の変化、保護者や学校、教員はどんな対応をすべきかがより詳しくまとめられている。
保護者クレーム 劇的解決「話術」(著:齋藤浩)
学校では、保護者からのクレームが常軌を逸したものになっており、対応に当たる教員が疲弊している。
「うちの子を注意しないで」「起きられないので毎朝電話して」「うちの子がリレー選手に選ばれないのはおかしいので、選考をやり直してほしい」など、個人の主義主張の押し付けや無理難題、驚くようなクレームが保護者から寄せられているという。
こうした理不尽なクレームや要求にはどう対応すればよいのか。神奈川県の公立小学校で児童支援専任教諭として児童指導に従事し、保護者トラブルに関する著書もある齋藤浩氏がまとめたのが、『保護者クレーム 劇的解決「話術」』(中央法規出版)だ。
齋藤氏には、「『非がなければ謝らず』、親の理不尽な苦情に毅然とした態度を取るべき理由」という記事でも取材をしているが、いったん保護者の言いなりに対応してしまうと、クレームがさらにヒートアップしたり、学校や地域を巻き込んだトラブルに発展することもあるという。
そうなる前に、最初の窓口である担任の先生のところで、しっかりと手を打つことが必要で、同書にはたくさんのヒントがまとめられている。
救え!!トイレの若手さん(著:前川智美)
学校現場では、働き方改革、教員のなり手不足、教員の休職や退職など、学校現場では難しい課題が山積している。
とくに慢性的な教員不足は深刻で、若手がチャレンジする機会はもちろん時間をかけて成長することが難しくなっている。若手教員の育成にまで手が回らないのはもとより、辞めてしまうことも珍しくない。



































