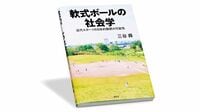「体育会系」学生3名のリアルな声、学業や就活との両立は?プロか就職か…? 卒業控えた運動部学生、三者三様の課題を聞く

練習が講義と被らないよう監督が配慮、プロも視野に就活
まず話を聞いたのは、八戸学院大学でラグビー部主将を務める4年生の廣瀬大翔さん。高校入学のタイミングで目にしたラグビーの試合をきっかけに自身もラグビーを始め、大学でも競技を続けてきた。

八戸学院大学 ラグビー部主将
(写真は本人提供)
大学生活では部活動が大きなウエイトを占めるものの、基本的には授業時間と被らないように監督が配慮してくれるため、実際に大きく困ったことはなかったという。
「ただ、教職課程を履修しているなどで講義数が多い部員の場合、夕方の練習時間と講義が30分ほど重なる日はあります。また、筋力トレーニングなどは講義前の朝の時間帯に行うので、1限目の講義がある日は体力的につらさを感じることもありました。自分は学業との両立を考えて、1日に10分でも20分でも予習・復習をする習慣を心がけていました」
八戸学院大学のラグビー部は、プロ選手も輩出している東北の強豪校だ。卒業後の進路を尋ねると、プロ選手を目指してセレクションを受けることを検討する一方で、就職活動にも取り組んでいるという。
「OBの方や先輩からは、『ラグビーを頑張っていれば報われる』と聞きますし、実際にプロになった先輩もいます。自分自身、ラグビーを続けたいという思いが強かったこともあり、就職を意識し始めたのは3年生の後半と遅めでした」
就活のために何度か練習を休まなければならず、仕方がないと思いつつも「ストレスだった」と廣瀬さんは語る。監督に確認して許可が出れば練習を休み、大事な練習や試合前は企業側に相談して時間をずらしてもらうなどで対応したそうだ。

(写真は本人提供)
「面接では、主将としてのチームのまとめ方をアピールしました。全員が同じプロセスを持つことが大事なので、共通認識を作るためにミーティングを設けたり、部員一人ひとりと会話したりしたことを話すと、悪くない反応をいただけた気がします。キャリアセミナーを通じて自己分析や業界研究のきっかけをもらったことで、自分では気づけなかった適性を知ることができ、就活や就職を前向きに検討できるようになりました」
就活支援を通じて、自身に「外交的でコミュニケーション能力がある」と知った廣瀬さん。自分としては意外な評価だったそうだが、部活動での経験が生きたという納得感はあり、興味を持てる業界や職種も広がったそうだ。面接では、部活動を経て気づいたコミュニケーションの重要性を伝えるようにしており、実際にコミュニケーション力を裏付けるエピソードは人事からも高評価なようだ。
平日の大会で「講義が公欠続き」に不安、指導者の理解が不可欠
続いて話を聞いたのは、富士大学ハンドボール部で選手として部活動に励んできた4年生の水野有彩さん。ハンドボールは小学校4年生から始め、10年以上の競技経験を持つ。高校卒業時、一度は競技を離れることも考えたが、富士大学の監督から声をかけられたことで継続する覚悟を決め、現在に至る。