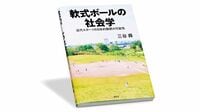「体育会系」学生3名のリアルな声、学業や就活との両立は?プロか就職か…? 卒業控えた運動部学生、三者三様の課題を聞く

(写真は本人提供)
就活ではタイムマネジメントが重要だという。面接や説明会の日程が練習と重なることも多く、練習を休まざるをえない日もあった。幸い、先輩やメンバーからの理解がある環境だったため、精神的な負担はそれほど大きくなかったものの、就活期間中はアルバイトも減らしていたため金銭的な不安は大きく、大会費の工面には苦労したそうだ。
「スポーツ学生に限らずですが、就活が実質3年生からスタートして4年生までの長期間に及ぶことで、精神的に疲れた感覚はありました。また、内定承諾の期限と『別の会社も受けたい』という思いがぶつかることもありましたね」
運動部学生を支える環境づくり、学生スポーツへの還元を
就活の長期化が、学生の学業や研究に影響を及ぼしているという話は聞く。おそらく、部活動の影響も無関係ではないだろう。学生は自分たちの将来を考えればこそ、学業・部活動にも、就活にも全力を注ぎたいはずなのに、どちらかしか選べないジレンマにさらされているのだ。
こちらの記事で話を聞いた、一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)の山田氏は、インタビューの結びで「スポーツの本質は、楽しむことです」と口にした。現代の日本では「これ」と決めたらその競技に集中して取り組むことが美徳のように思われがちだ。しかし、「本来はもっといろいろなスポーツに挑戦してよいし、いろいろなタイミングでそれを楽しんでほしい」と山田氏は語った。

一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS) 広報部 部長
(写真は本人提供)
「スポーツに関わる方法は、競技者以外にもたくさんあります。例えば、勤務先がどこかのチームのスポンサーをしているかもしれないし、社会活動としてスポーツを奨励しているかもしれない。スポーツに関わる場面がたくさんあることで、スポーツ自体の裾野もどんどん広がっていきます」
運動部学生のキャリアは、部活動の経験から得られた力で切り開かれていく。これを支えるのはコーチや指導者、そしてファンたちだ。学生時代に競技者として、観覧者として、その他さまざまな形でスポーツを愛してきたファンたちが、社会人になって学生スポーツに還元していく。この好循環を回し続けるためにも、スポーツに興味を持った子どもや若者たちが臆せずそのキャリアを歩める環境を作ることが、今後さらに重要となるのかもしれない。
(文:藤堂真衣、注記のない写真:Anthony / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら