ロケット、ロボット…「ホンダイズム」の現在地。4輪車メーカーでなくなる日は来るのか
再使用型ロケットはイーロン・マスク氏率いる米スペースXが手がけており、日本ではJAXA(宇宙航空研究開発機構)も開発に乗り出している。
だが国内民間企業としては、これが初めての快挙だった。ホンダが持つ技術力、チャレンジ精神を改めて示す出来事となった。「事故が起きた場合のリスクを考えて、『ホンダ』とわかるようなロゴを役員が付けさせなかったようだ」という逸話も残りはしたが。
今後ホンダは、2029年に高度約100キロメートルの「準軌道」到達を目指す。
ほかにも「空飛ぶ車」と呼ばれるeVTOL(イーブイトール)(電動垂直離着陸機)や、世界シェア首位を記録した小型ビジネスジェット「ホンダジェット」の新型機、アシモの技術を応用した遠隔操作ができるヒト型ロボットなどにも着手。いずれも独立した研究開発子会社・本田技術研究所が主導している。
4輪車にこだわらない
「海や地上、空など空間を移動するものすべてがモビリティー。そのくくりであればわれわれの本業だ」。三部社長は今回のインタビューで、事業の根幹をそう位置づけた。超長期では必ずしも4輪車にこだわらない──。その言葉からは、トヨタ自動車や日産自動車といった同業他社とは異なる道を歩むのだという自負がにじむ。
モビリティービジネスに詳しい伊藤忠総研の深尾三四郎主席研究員は、「ホンダはベンチャー精神の塊として、誰にもできない領域を1つずつ増やしてきた。月面で継続的に水を生み出す循環型エネルギーシステムも手がけている。月面では移動より水に価値があるという発想はホンダならではだ」と語る。
今後はビジネスの種を果実へと育て、摘み取れるかが焦点になる。
EVを筆頭に、巨額投資と長期開発が前提となりがちな事業環境の中、技術の可能性をどう見極めるかは悩ましい。ホンダジェットは納入に約30年、ホンダのHV(ハイブリッド車)も収益性が向上するまでに20年以上の歳月を費やした。中長期の研究開発には株式市場から厳しい視線が注がれる情勢も、見通しを難しくしている。
ホンダの初代副社長である藤澤武夫氏は、他者に依存せず自ら切り開く重要性を説き「たいまつは自分の手で」という言葉を残した。ホンダが次に掲げるたいまつはどこへ向かうのか。挑戦の火を絶やさず、再び世界を驚かせられるかが問われている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

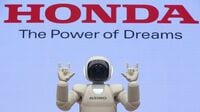





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら