日本はサンマが実質"獲り放題"になっている…「海水温上昇」「外国漁船」「暖水塊」よりも根本的な不漁原因
ただし漁獲枠が機能してくると、今度は数量を実際はそれより多く漁獲していても「枠の通り」と申告してくる可能性はなくもありません。それは、かつて1977年に200海里漁業専管水域が設定された際に、我が国がアメリカ内で操業許可を受けていた際に申告量を少なめにしようとしたのと同じことになりかねません。歴史は繰り返します。
なお、筆者はかつてイギリスのサバ他でも同じようなごまかしが起きて、その後に大きな問題になったことを現場で見てきました。そして、ごまかしが収まるとサバ資源は徐々に回復に向かいました。欧州であろうと世界のどこであろうと漁業者や水産関係者が考えることは同じです。
今年(2025年)の公海でのサンマ漁獲枠は12万トンとなり昨年の10%減となります。これ自体は漁獲枠自体が大きすぎることに変わりありません。しかしながら、漁獲量が公海での漁獲枠に達することで制限されれば、従来獲られてしまっていた一部が、生き残って次年度以降に資源をつないでいく可能性があります。もちろん自然死や捕食される分もありますが、それらを考慮しても、稚魚放流の資源管理手法とは効果がけた違いです。
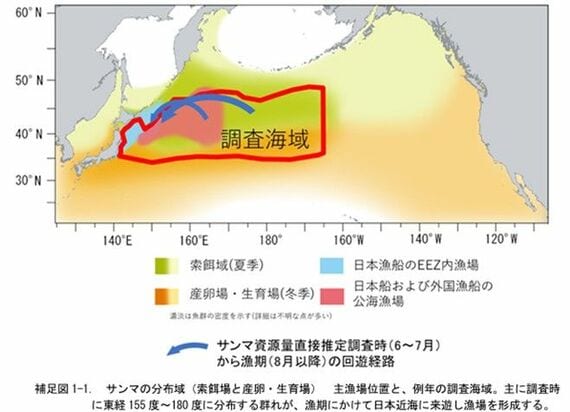
国際枠は機能したが、日本枠はいまだ「獲り放題」
さて、資源がやや回復傾向にあり、依然大きすぎるものの、「公海での漁獲枠」が機能しそうな雰囲気があります。しかしながらその資源回復に水を差してしまう可能性があるのが、「日本の漁獲枠」なのです。なお、筆者の視点はわずか数年良ければよいという短期的ものではありません。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら