「コロナ世代は可哀想」と大人たちは言うが…映画『この夏の星を見る』などコロナ禍を見つめ直す作品が増える背景
茨城と東京をつないだのは、指定された天体を望遠鏡で素早くキャッチする競技「スターキャッチコンテスト」。初のリモートによるコンテスト開催を機に知り合った茨城、東京、さらに長崎を加えた3校の学生たちは、それぞれの地で今できる精一杯を模索する──。


一斉休校による自宅待機にはじまり、部活動の短縮、昼休みの黙食、そしてもちろん、マスク着用(映画でもきっちり徹底されている)に至るまで、制約の多かった当時の学生生活を、これほど詳細に記録した作品はほかにないだろう。
なかでもハッとさせられたのは、この映画がコロナ禍に存在した特定職業への偏見や差別を、大人ではなく子どもたちの目線から描いたことだ。
「旅館の家の娘」に向けられた偏見の目
物語の第3の舞台、長崎県・五島列島の高校に通う佐々野円華(中野有紗)の実家は、小さな旅館を営んでいる。
県外客を受け入れる佐々野家の旅館に、冷たい視線を送る住民は少なくない。あるときから円華の家には、コロナ禍の営業を非難する嫌がらせの張り紙がいくつも貼られるようになっていた。

学校でいつも一緒に行動していた親友の福田小春(早瀬憩)からも、一時的に距離を置きたいと実質的な拒絶を受けることに。小春の家には、高齢の祖父母と介護施設で働く姉がいる。事情を知った円華は何も言えずただ傷つき、2人の間には気まずい距離が生まれてしまう。
小春は小春で、家庭内や周囲の空気に押されてそうするしかなかったのだ。相手を責めるわけでもなく喧嘩もできずにすれ違う、そんな当時特有のディスコミュニケーションがこの場面にはよく表されている。
コロナ社会の歪みが10代に与えた心の痛みは、これまで作品の中でなかなか取り上げられてこなかった。この世代が語られるとき、よく使われる「コミュニケーションの希薄化」という言葉の中にも、実際は一人ひとり複雑な背景がある。
コロナが奪い去ろうとする青春の日々を、スターキャッチを通じて自分の力で取り返すべく奔走する学生たちの姿は逞しく、頼もしい。この世代を「可哀想」「気の毒」といった言葉で単純化しないという物語の意志が、登場人物たちの姿の奥に感じられた。




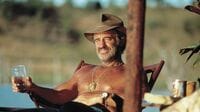



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら