「AIが描けない未来を創る!」新しい世界を切り拓く違和感の鍛え方
例を挙げると、インスタントラーメンの発明は、日清創業者の安藤百福が、冬の寒い日に闇市でラーメンの屋台に並ぶ人々を見かけた際に、「家庭で手軽にラーメンが作れれば、寒い思いをしなくて済むのに」と感じたことが、一つのきっかけになっていると言われています(諸説あるようですが)。
もしそのとき、彼が「いや、ラーメンってのはそういうものだ」と考えてその思いを振り払ってしまったり、あるいは「寒い思いをさせる分、美味しいラーメンを提供してほしいな」としか感じていなかったりしていたら、インスタントラーメンは永遠に生まれなかったか、生まれていても今ほど広まっていなかったかもしれないのです。
そう思えば、日常に感じる小さな違和感に気づき、それを真剣に考えることの重要性が、おわかりいただけることと思います。
「独自の世界観」を重視し、大切に育てていくべき
人間はそもそも、自分だけの経験を積み重ね、自分だけの価値観やものの見方を獲得していく存在です。
同じ学校のサッカー部に所属して同じ試合に出場すれば、メンバーの誰もが同じ経験をするかと言えば、そんなはずはありません。その試合で最も記憶に残ったこと、腹が立ったこと、嬉しかったこと、どれも一人ひとり違うはずです。
同じ時間に東京駅の同じ通路を歩いていても、毎日通勤で使う人と出張でたまたま利用した人、海外からの観光客など、その目的は多種多様。当然、駅を歩いて感じることも、一人ひとりまったく違うことでしょう。
こうした唯一性の高い経験を積み重ねることで形作られた「主観」は、AIにはもちろん、自分以外の誰にも代わりが務まらないものです。そして、この主観が独特であればあるほど、他の人とは異なる独自のものの見方が形成され、他の人には見えない「違和感」が見えるようになってきます。
ラーメン店の行列を見て、安藤百福は、「家庭で手軽に食べられるラーメンを作ろう。家でサッとラーメンが食べられる世界は素晴らしい」という未来を思い描きました。
しかし、人によっては別の未来を思い浮かべるかもしれません。
「行列に並ぶ人たちの時間、無駄だな。発電とか、何か生産性のあることに活かすことはできないか?」というような妄想を浮かべるかもしれない。
確かに、そうした突飛な発想が実現可能なアイデアに結びつく例は決して多くはありませんが、それでいい、むしろそれがいいのです。
そうした「違和感」「ズレ」への嗅覚を養った先に、新たな世界を切り開くアイデアが、きっと頭の中に降ってきます。
今こそ、自分なりの主観によって強化された情報の連なりによって生まれる「独自の世界観」を重視し、それを大切に育てていくべきなのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

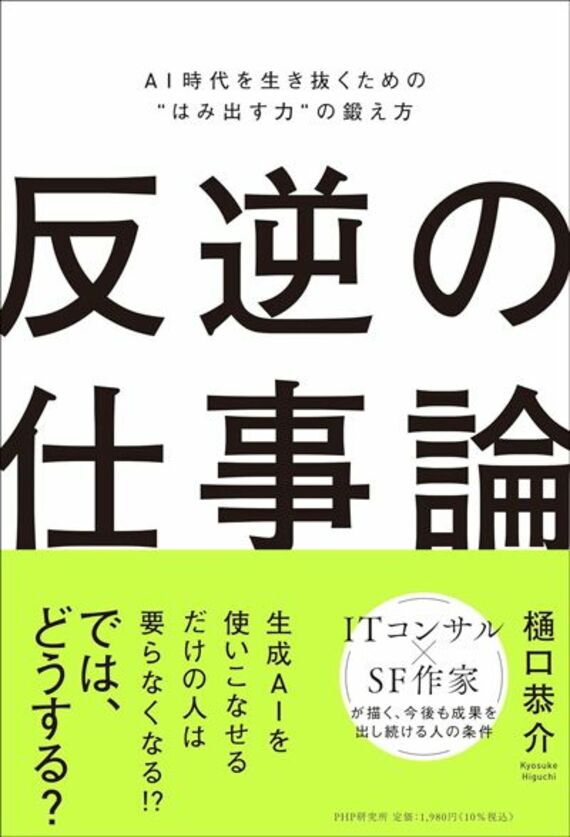
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら